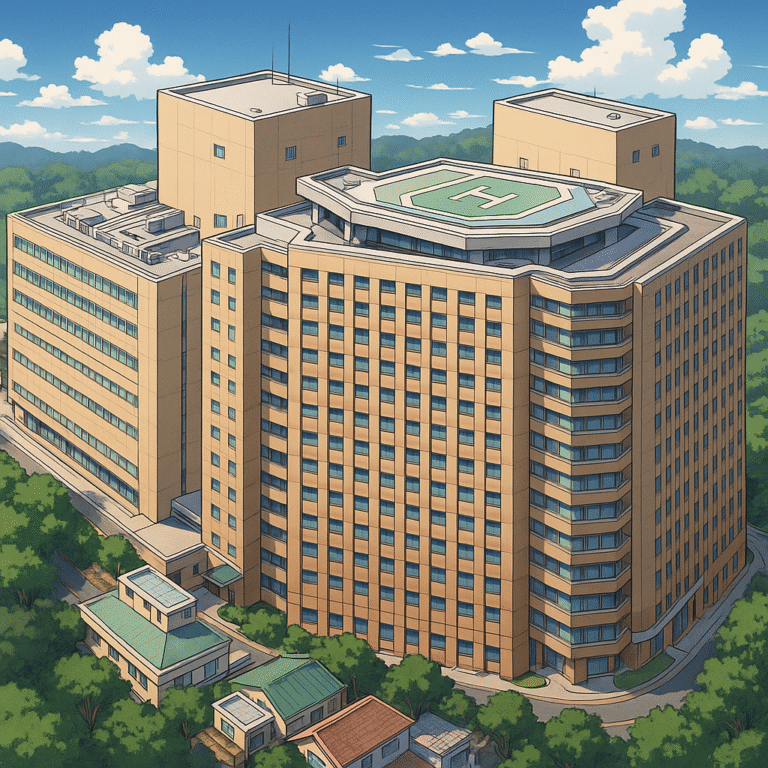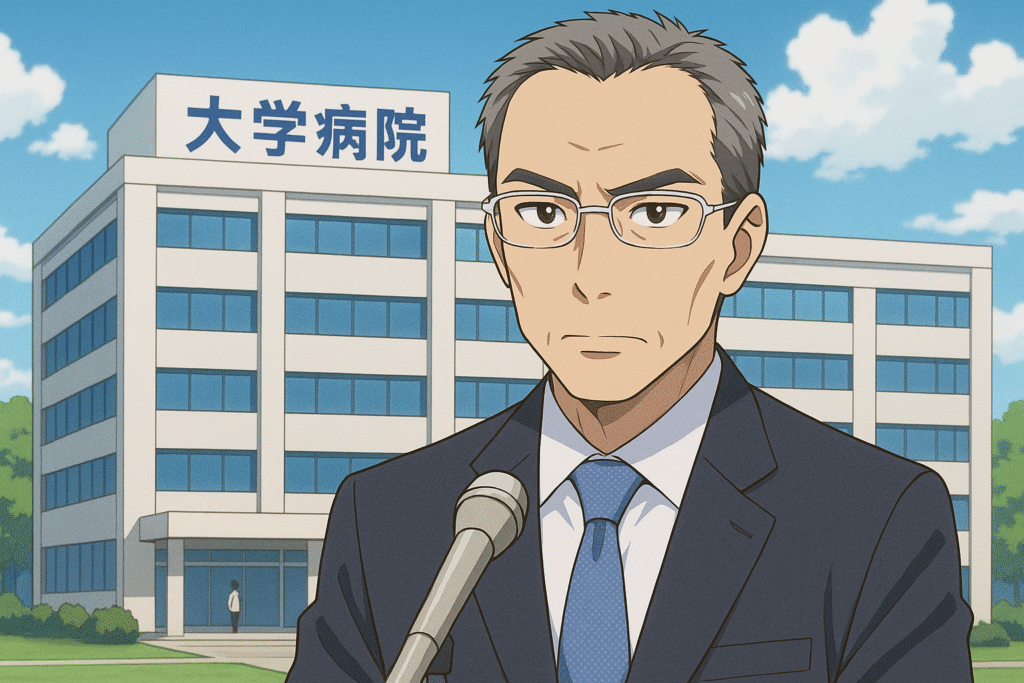
※最新ニュース
国立大学病院が抱える深刻な経営危機とは?

2024年度、全国の国立大学附属病院が記録的な赤字に陥りました。
NHKの報道によれば、全国44の国立大学病院のうち、なんと約7割が赤字経営となり、その赤字総額は過去最大の285億円にまで達したといいます。これは前年度のおよそ5倍という、かつてない規模の経営悪化です。
背景には、複数の深刻な要因が絡んでいます。
ひとつは、物価や人件費の高騰。医療現場では、高性能な医薬品や診療材料の価格が上昇しており、さらに人手不足の中で人件費の引き上げも避けられない状況にあります。
一方で、病院の主な収入源である診療報酬(医療行為に対する国からの支払い)は大きく増えていないため、収入と支出のバランスが崩れているのが現状です。
たとえば、2024年度は収益自体は増加しているものの、支出の増加ペースがそれを大きく上回ったことで、結果的に赤字が急増する事態となっています。
さらに、2004年の「国立大学法人化」以降、各大学病院は自立的な運営を求められ、従来のような手厚い国からの補助金が減少しています。
その結果、大学病院は「高度医療・教育・研究」という三重の責任を負いながらも、経営的には民間病院と同じ土俵で戦わなければならなくなりました。
このような制度的背景と経済環境の変化が重なった今、大学病院では「医療機器の更新ができない」「スタッフの確保が困難」「学生・研修医の教育にも影響が出ている」といった声が現場から上がってきています。
このニュースは、単なる経営データの話にとどまりません。
医師を育て、地域の高度医療を担う大学病院が機能不全に陥るということは、将来の医療そのものが揺らぐ可能性があるという、非常に大きな警鐘なのです。
※SNSの反応
kukurukakara
“医療現場では、新たな医療機器の購入や老朽化した設備の更新ができないといった問題が起きている。このまま支援がなければ、大学病院は間違いなく潰れてしまう”
restroom
“政府は、稼げる大学、とか言い出して、大学に独自の収入を増やすように求めています。大学病院の収入はその貴重な財源だったのですが、赤字では完全に破綻です。”
yamada_k
“物価や人件費の上昇が原因なら国立大学病院だけの問題ではない。”
🐦 X(旧Twitter)の反応
eeeco_ms88
“国立大学病院がほぼ赤字ときいて納得しかないし、医療の質落ちてももうだれも文句言えない状態に来てる。病院に文句言っても無駄です。”
Sputnik 日本
“全体の約7割にあたる29病院が赤字となり、赤字総額は…285億円となった。”
iida__kenichi
“命を支えるはずの大学病院が── ‘やればやるほど赤字’という地獄のような現実。筑波大学附属病院:28億円の…”
背景には何があるのか?? 何が問題になるのか?

「大学病院が赤字」と聞いても、患者や一般の方にはピンとこないかもしれません。
しかし、この問題が進行すると、私たちの身近な医療や医師の育成、地域医療の体制にも深刻な影響が及びます。
🔻 影響①:医療の質が維持できない
大学病院は、がん治療や高度外科手術、救命救急など高度で専門的な医療の拠点です。
しかし、経営が逼迫すれば…
- 最新の医療機器が購入できない
- 診療材料費のコストカットで選択肢が狭まる
- 医療スタッフの確保が困難になる(待遇・人員不足)
といった状況になり、医療の質そのものが低下してしまいます。
とくに「大学病院にしかできない治療」が提供困難になることは、患者にとって命に関わる大問題です。
🔻 影響②:医師の教育・研究が滞る
大学病院は、未来の医師を育てる場であり、医学研究の中心でもある重要な施設です。
しかし今、現場では…
- 教育用の教材や設備の更新が難しくなる
- 教育や研究に充てる人的・金銭的余裕が失われつつある
- 忙しすぎて若手が「教育より日々の業務優先」に
といった課題が顕在化しています。
結果として、医師の“質”の低下や、日本の医学研究力の低下にもつながりかねません。
🔻 影響③:地域医療・災害医療の拠点が崩れるリスク
大学病院は単なる「大病院」ではなく、地域医療の最後の砦でもあります。
特に災害時には基幹病院として機能し、地域住民の命を守る役割を担っています。
しかし、今回の赤字問題が進行すれば…
- 救急受け入れ体制の縮小
- 難病や希少疾患患者のフォロー困難
- 地方での「医療空白地帯」の拡大
といった「地域の医療インフラ崩壊」が現実化してしまうかもしれません。
🔍 背景にある3つの根本課題
このような問題がなぜ今、深刻化しているのか?
背景には以下の3つの構造的課題が絡んでいます。
① 診療報酬制度と実情の乖離
診療報酬は国が定めたルールに基づき、医療行為に対して支払われるお金です。
しかし、この制度は物価や人件費の上昇に十分に対応しておらず、現場では「やればやるほど赤字になる」という声が上がっています。
特に大学病院では、手間とコストがかかる高度医療が多いため、報酬の割に負担が重く、採算がとれません。
② 国立大学法人化による「自立経営」のプレッシャー
2004年の国立大学法人化によって、国立大学病院は従来のような手厚い国の補助から離れ、独自の収入での運営を強いられるようになりました。
教育・研究・診療という“三本柱”を担いつつも、収益性まで求められる構造に、現場からは「限界だ」という声が上がっています。
③ 人件費・物価の高騰と慢性的な人手不足
コロナ禍を経て、医療人材の確保は全国的に厳しさを増しており、看護師や薬剤師の給与引き上げや勤務体制の改善は不可欠です。
一方で、物価や円安の影響で医薬品・機器も値上がりし、支出が膨らみ続けているのが現状です。
収益増が追いつかないままコストだけが増えれば、当然赤字は拡大します。
大学病院“崩壊”を防ぐために──今、現実的にできる5つの対策
前章で述べたように、国立大学病院の経営は深刻な危機に直面しています。
しかし「仕方ない」で済ませるわけにはいきません。
医療の中核を担う大学病院を守るためには、**今すぐにでも着手できる“現実的な対策”**が必要です。
ここでは、その中でも実行可能性が高く、効果が期待できる解決策を5つご紹介します。
✅ ① 診療報酬の柔軟な見直しと加算制度の充実
診療報酬が現在の医療実態に見合っていないことが最大の課題です。
大学病院は、高度・多様・多職種連携が必要な診療を多く担っており、その負担を反映した診療報酬体系が必要です。
🔹具体的対策:
- 高度医療や救急医療に特化した**「大学病院加算」**の強化
- 教育・研究機能を持つ病院への基礎的加算の新設
- 効率化を阻害しない範囲での、診療報酬の段階的見直し
これは診療報酬改定のタイミング(2年に一度)で現実的に議論可能です。
✅ ② 国による「教育・研究病院」への直接的財政支援の再構築
大学病院は単なる医療提供機関ではなく、**未来の医師を育て、研究を進める「社会資本」**でもあります。
この機能に対しては、市場原理だけで支えるのではなく、国による直接支援が不可欠です。
🔹具体的対策:
- 「教育病院支援枠」「研究連携病院補助金」などの明確な制度整備
- かつて存在した運営費交付金の一部復活や拡充
- 補助金対象を、病床数や診療収益に比例させず、「機能評価ベース」に変更
これは文科省や厚労省が連携する形で、政策的に進めやすい分野です。
✅ ③ ICT導入による業務効率化と事務負担軽減
大学病院の多くは、煩雑な書類業務や手作業での事務処理が多く、現場の負担になっています。
AIやICTを活用することで、医師・看護師の本来業務に集中できる体制を整えることが急務です。
🔹具体的対策:
- 電子カルテのクラウド一元管理
- AIによる書類作成支援・病名コード自動化
- 病院内オペレーションの可視化・最適化(病床回転率・人材配置など)
中長期的な投資が必要ですが、すでに民間病院で効果が出ている事例も多くあります。
✅ ④ 医療人材の確保と処遇改善の支援制度
人件費高騰が赤字の主因でもある中で、「安く雇えばいい」という発想では現場は崩壊します。
だからこそ、人材への投資を「持続可能に行える支援」が必要です。
🔹具体的対策:
- 地域医療支援センターなどによる人材循環・再配置支援
- 若手医師・看護師のキャリア支援補助制度の拡充
- 労働時間適正化のためのチーム医療体制強化(タスクシフト推進)
✅ ⑤ 国と大学の「経営マネジメント支援」体制の構築
多くの大学病院では、「臨床・研究のプロ」はいても「経営のプロ」が不足しています。
現実的には、大学病院の経営は民間並みに複雑で、専門性が高いため、支援チームの常設が必要です。
🔹具体的対策:
- 各病院に経営戦略専門官(外部登用)を配置
- 文科省や厚労省と連携した「大学病院経営アドバイザリーチーム」の創設
- データ分析・経営改善を伴走支援する国主導の第三者機関の設立
これは予算化とモデル病院の設置からスタートできる、現実的な提案です。
最後に・・・
医療現場だけでなく他の職種の方でも、近年の世界的な物価上昇の影響でこのような問題が起きているのではないでしょうか。
会社や病院ありきの私たちなので、経営が大事ですが、
実際の医療の場でも、働き方改革という名の時間外削除の圧力などで給料は少しずつ下がっています
自分の仕事場だけでなく、他の病院の先生にも同じような話を聞きました。
給料も上がらず、病院の経営もかなり厳しい状態です。
問題を挙げたり、文句を言うのは簡単です。一人一人が解決策を考えなければかわらないでしょう。
今の政治にはなかなか期待できないので・・・・
KOY