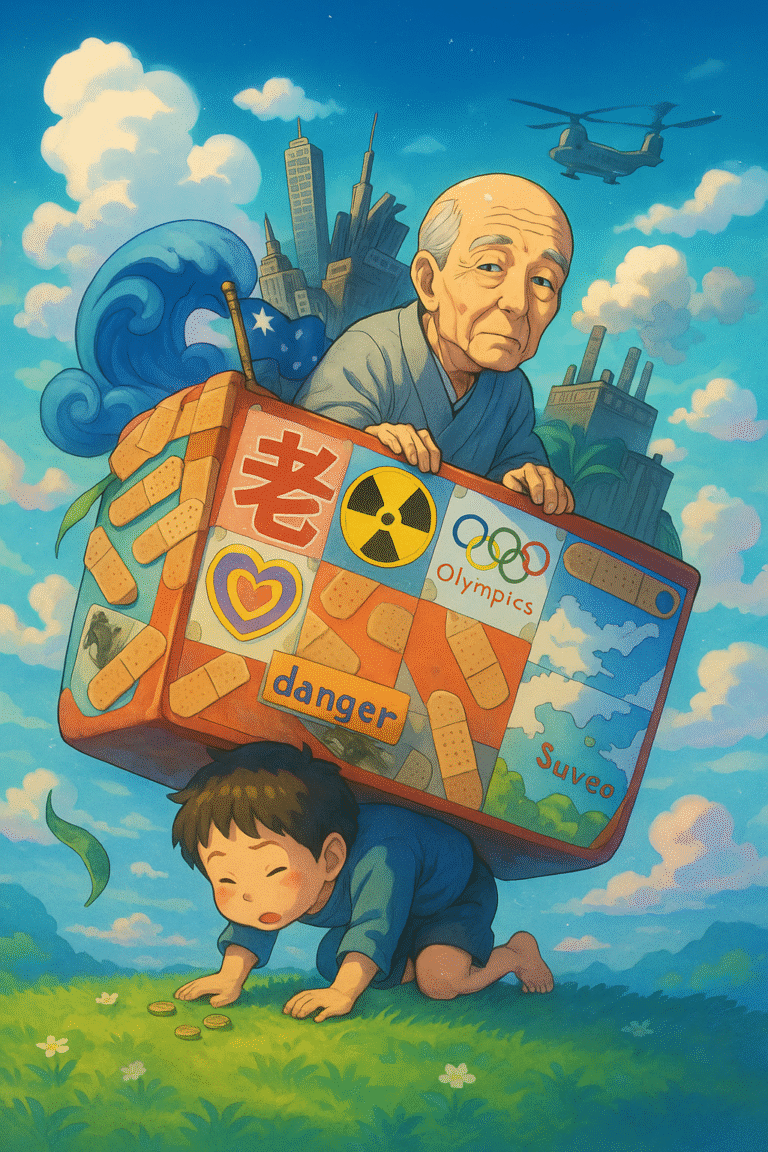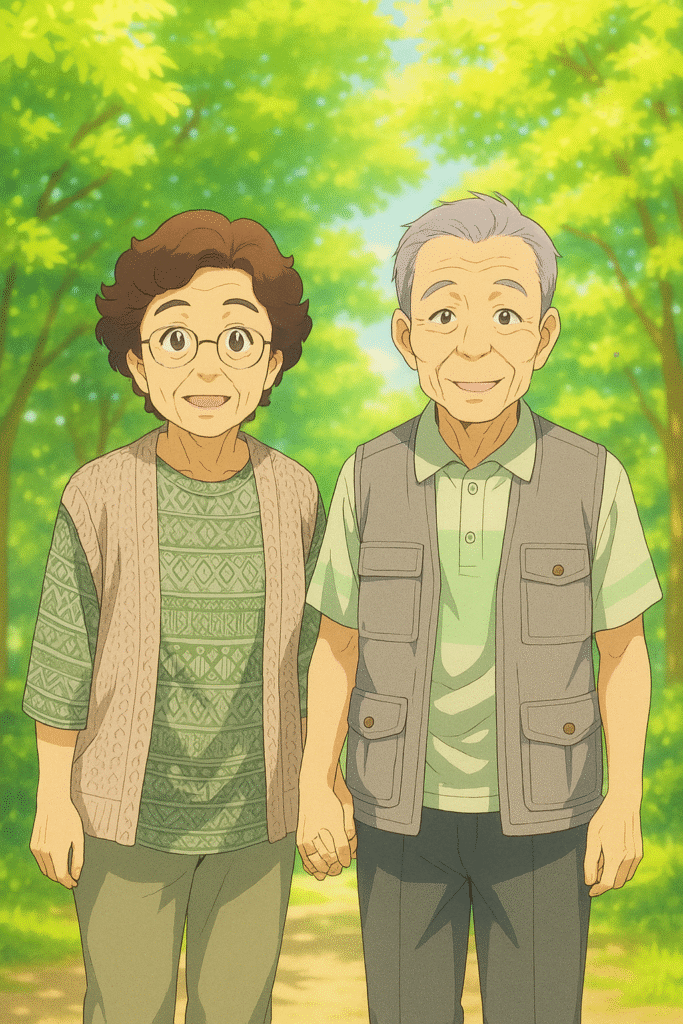

2025年9月。厚生労働省が発表した最新のデータによると、日本国内の100歳以上の高齢者数が95,119人に達したと報告されました。
これは前年より2,980人多く、実に55年連続で過去最多を更新しています。さらに注目すべきは、そのうち88%が女性であるという点です。
「100歳まで生きるなんて、一部の特別な人だけでしょ?」そう思っていた時代は、もう過去のものになりつつあります。
今や100歳は「夢」ではなく「現実」に。では、どうすれば健康的に、そして前向きに年齢を重ねていけるのでしょうか?
本記事では、この驚きのニュースをきっかけに、長寿の背景と「長生きする人たちの共通点」についてお伝えします。
ニュース:100歳以上は9.9万人=55年連続増、女性が88%―厚労省

厚生労働省は12日、全国の100歳以上の高齢者が1日時点で9万9763人に上り、55年連続で過去最多を更新したと発表した。住民基本台帳に基づく集計で、昨年より4644人多く、女性が8万7784人と全体の約88%を占めた。
100歳以上の高齢者は、統計を取り始めた1963年は153人だったが、81年に1000人、98年に1万人を突破。2012年に5万人、22年に9万人を超え、今年10万人に迫った。
人口10万人当たりの100歳以上の人数は80.58人。都道府県別で見ると、島根が168.69人と13年連続で最多となり、高知(157.16人)、鳥取(144.63人)が続いた。最少は埼玉(48.50人)で、愛知(53.00人)、大阪(55.44人)の順に少なかった。
国内最高齢は、女性が114歳の賀川滋子さん(奈良県大和郡山市)で、男性は111歳の水野清隆さん(静岡県磐田市)。1973年にノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈氏も、今年3月に100歳を迎えた。
今年度100歳を迎える人は5万2310人。対象者には祝い状と銀杯が贈られる。
◇100歳以上の都道府県別人数
100歳以上 人口10万人当たり (順位)
北海道 5157 102.26 (26)
青 森 959 82.32 (35)
岩 手 1284 112.14 (17)
宮 城 1828 81.32 (36)
秋 田 962 107.25 (21)
山 形 1199 118.60 (12)
福 島 1794 102.93 (25)
茨 城 2096 74.70 (40)
栃 木 1421 75.38 (39)
群 馬 1598 84.55 (33)
埼 玉 3556 48.50 (47)
千 葉 3580 57.27 (44)
東 京 8150 57.48 (43)
神奈川 5386 58.38 (42)
新 潟 2538 120.91 (11)
富 山 1070 107.32 (20)
石 川 1018 92.71 (27)
福 井 762 103.11 (23)
山 梨 919 116.18 (14)
長 野 2661 133.92 (5)
岐 阜 1706 89.04 (29)
静 岡 3025 85.77 (31)
愛 知 3954 53.00 (46)
三 重 1449 84.69 (32)
滋 賀 1026 73.18 (41)
京 都 2209 87.66 (30)
大 阪 4855 55.44 (45)
兵 庫 4109 76.99 (38)
奈 良 1158 90.12 (28)
和歌山 961 109.20 (19)
鳥 取 768 144.63 (3)
島 根 1083 168.69 (1)
岡 山 1886 103.00 (24)
広 島 2864 105.53 (22)
山 口 1606 125.37 (7)
徳 島 760 110.95 (18)
香 川 1031 112.43 (16)
愛 媛 1563 122.49 (9)
高 知 1031 157.16 (2)
福 岡 4295 84.35 (34)
佐 賀 889 112.82 (15)
長 崎 1567 125.16 (8)
熊 本 2254 132.82 (6)
大 分 1323 121.94 (10)
宮 崎 1225 118.59 (13)
鹿児島 2091 136.49 (4)
沖 縄 1137 77.56 (37)
全 国 9万9763 80.58 (C)時事通信社
第1章:100歳以上が9.9万人!その背景にある日本の姿
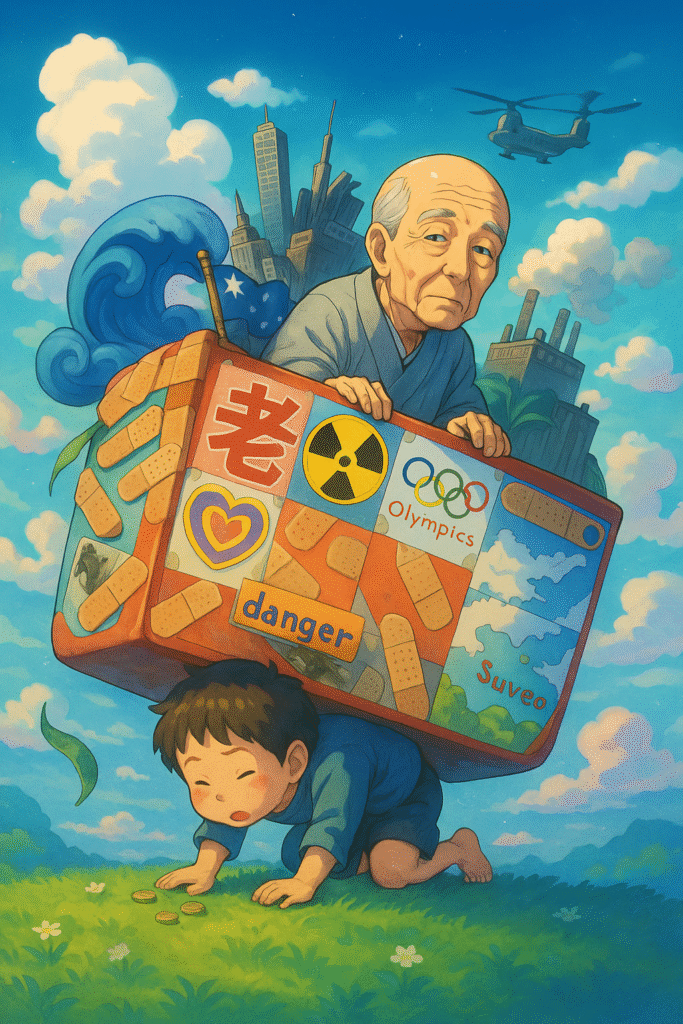
◆日本は世界トップクラスの長寿国
2024年の時点で、日本人の平均寿命は女性87.1歳、男性81.2歳と、世界でもトップレベル。今回の調査では、100歳以上の高齢者が**9.9万人(男性1.1万人、女性8.8万人)**に達したことが明らかになりました。
この現象には、さまざまな要因が関係しています。
- 医療技術・介護制度の発展
- 公衆衛生の向上
- 食生活の多様性と栄養バランス
- 予防医療の推進(健康診断、ワクチンなど)
- 国民皆保険制度と医療アクセスの良さ
◆女性が多いのはなぜ?
100歳以上のうち、実に88%が女性。これは生物学的・社会的な要因が複合的に関係していると考えられています。
- 女性ホルモン(エストロゲン)による血管保護作用
- 男性に比べて健康管理や受診率が高い傾向
- 社会的なつながりを持ちやすい(地域活動や会話など)
- アルコールや喫煙習慣が男性より少ないことも一因
もちろん個人差はありますが、統計的には女性の方が健康的な生活習慣を維持しているケースが多いのです。
第2章:100歳まで生きる人に共通する「長生きのコツ」
長生きする人々には、いくつかの共通点があります。ここでは、医師としての視点と、科学的根拠に基づいて「健康寿命を延ばす」ために意識すべきポイントを紹介します。
① 食事:和食・バランス・腹八分目
- 植物性中心の食事(野菜、豆腐、海藻など)
- 魚の摂取が多く、オメガ3脂肪酸が豊富
- 発酵食品(納豆、味噌、漬物)をよく食べる
- 塩分・脂肪控えめ
- 食べ過ぎず、「腹八分目」を守る習慣
長寿地域(沖縄や長野など)でも共通して見られる傾向です。
② 運動・活動:無理なく体を動かす
- 毎日散歩や畑仕事をしている
- 階段を使う、掃除をするなど「日常生活での活動」が豊富
- 軽い体操やラジオ体操など、継続できる運動を習慣化
激しい運動は不要ですが、「座りっぱなし」を避けることが大切です。
③ 睡眠・休養:質の良い睡眠で回復力UP
- 就寝・起床時間が規則的
- 日中はよく動き、夜はぐっすり
- 昼寝を上手に取り入れることで認知症リスクも軽減
スマートフォンや強い照明を避け、リラックスできる寝室環境も大切です。
④ 心の健康:社会とのつながりが鍵
- 地域活動や趣味に参加している
- 友人や家族とよく話す
- 笑いの多い生活をしている
- 「生きがい」がある(孫との交流、趣味、手芸など)
孤独は高齢者の健康にとって大きなリスク。人との関わりが“元気の源”になります。
⑤ 医療との付き合い方:定期的なチェックと早期対応
- 健康診断を欠かさない
- 血圧、血糖、コレステロール値などの自己管理
- 気になる症状があれば早めに受診
「病気になる前に見つけて対処する」姿勢が、健康寿命を延ばす秘訣です。
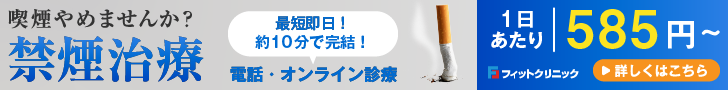
🧩 第2章「長生きのコツ/秘訣」まとめ表
| 項目 | 内容・特徴 | 実践ポイント |
|---|---|---|
| ① 食事 | – 和食中心(野菜・魚・海藻・発酵食品) – 腹八分目、塩分控えめ | ・毎日の食事に豆腐・野菜・魚を取り入れる ・発酵食品(味噌、納豆など)を意識 ・間食や夜食は控えめに |
| ② 運動・身体活動 | – 散歩、畑仕事、体操など – 無理なく継続できる運動 | ・毎日少しでも歩く(例:6,000歩) ・テレビ体操や軽い筋トレを習慣に ・階段や家事での活動も大切に |
| ③ 睡眠・休養 | – 規則正しい生活リズム – 睡眠の質を高める環境作り | ・就寝・起床時間を一定に ・寝室の光や音を調整 ・昼寝やリラックス時間も活用 |
| ④ 心の健康・社会的つながり | – 会話や交流、趣味の時間が多い – ストレスをためにくい | ・週に1回でも人と話す ・趣味(読書・音楽・手芸など)を持つ ・笑う、感謝する、ポジティブ思考 |
| ⑤ 医療との付き合い方 | – 健康診断を受けている – 病気の早期発見・対応 | ・年に1回は健診を受ける ・血圧・血糖値などを把握 ・不調があれば早めに受診 |
| ⑥ 生活環境・制度の利用 | – 安全な住環境、制度の活用 – 地域との連携あり | ・段差や転倒防止を意識した住まい ・介護・医療制度を知っておく ・地域の活動や相談窓口を活用 |
第3章:百寿者の実例に学ぶ 〜“特別なことはしていない”が実はすごい〜

◆百寿者とは?
「百寿者(ひゃくじゅしゃ)」とは、100歳以上の高齢者を指す言葉です。厚生労働省の発表によると、2025年現在、日本の百寿者は95,119人。そのうち女性が88%を占めており、日本はまさに「世界有数の長寿大国」と言えます【※1】。
では、この100歳を超えてなお元気に暮らす人たちは、一体どんな生活を送っているのでしょうか?ここでは、実際の百寿者のインタビューや調査から見えてきた共通点や生活習慣をご紹介します。
◆百寿者の声に耳を傾ける:「特別なことはしていないよ」
長野県で一人暮らしを続ける103歳の女性は、新聞の取材に対してこう語っています。
「ご飯は毎日しっかり食べて、畑に出て、テレビを見て寝るだけ。特別なことは何もしとらんよ。」
この「特別なことはしていない」という言葉、実は多くの百寿者に共通しています。そしてそれは、言い換えれば「普通のことを、長く続けてきた」という証でもあります。
同様に、全国の百寿者1,000人を対象とした厚生労働省「百歳高齢者調査」(平成25年版)では、次のような傾向が示されました【※2】。
| 項目 | 内容 | 割合 |
|---|---|---|
| 食生活 | 「規則正しく3食食べる」が多数 | 約80% |
| 運動習慣 | 「日課として体を動かしている」 | 約60% |
| 社会参加 | 地域の活動・家族との交流が活発 | 約70% |
| 睡眠 | 毎日同じ時間に寝起きする | 約85% |
| 趣味・娯楽 | 園芸、手芸、テレビ、音楽など多様 | 多数が回答 |
◆共通するキーワード:「柔軟さ」「好奇心」「感謝」
百寿者の言葉やエピソードを見ていると、以下のような**“心の持ち方”**にも特徴があります。
- 柔軟さ:「若い人のやり方も見てると面白いよ」「失敗しても、まあいいさ」
- 好奇心:「スマホを使えるようになった」「字が見にくいけど新聞は毎日読む」
- 感謝の気持ち:「毎日がありがたい」「人に助けてもらって今がある」
年齢を重ねても「変化を恐れず」「人と関わり」「心を豊かに保つ」ことが、健康長寿につながっていると感じさせられます。
また、“自分が役に立っている”という実感も重要です。例えば、農作業や家事を続けている方の中には、
「まだまだやれることがある」「誰かのために生きている感じがする」
という言葉を口にする人が多く、これは「自己効力感」や「社会的役割」が長寿の支えとなっている証です【※3】。
◆実例:世界最高齢の方々の生活
◉ 田中カ子さん(享年119歳、福岡県)
ギネス世界記録に認定された日本人女性・田中カ子さんは、晩年も毎日**「コーラを飲むのが楽しみ」**と語っていました。趣味は数学の問題を解くことやボードゲーム。施設のスタッフともよく笑って会話していたそうです【※4】。
→ 彼女の例からも、「小さな楽しみ」や「知的好奇心を失わないこと」が心身に良い影響を与えていたと考えられます。
◆まとめ:百寿者が教えてくれる「日常のすごさ」
百寿者の生活は、決して特別な健康法や最新の医療に頼っているわけではありません。
むしろ:
- 食べて
- 動いて
- 笑って
- 感謝して
- 眠る
という、あたりまえの日々をコツコツ積み重ねることが、最大の秘訣です。
それはまさに、「長生きのために頑張る」よりも、「自然体で暮らす」ことの価値を私たちに教えてくれます。
【参考・情報源】
- 【※1】厚生労働省.「令和6年敬老の日にちなんだ100歳以上の高齢者の状況」(2024)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43585.html - 【※2】厚生労働省.「100歳高齢者調査報告書」(平成25年)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000029429.html - 【※3】日本老年学的研究所「長寿者の生活実態と幸福感」調査
https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/long-life.html - 【※4】NHK.「119歳・田中カ子さん死去 世界最高齢の日本人女性」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220425/k10013597601000.html
まとめ
100歳以上が9.9万人に達したという事実は、「長生き」が珍しいことではなくなった時代の象徴です。
長生きの秘訣は、意外にも「特別なこと」ではありません。
- 食事を整える
- 毎日少しでも体を動かす
- よく眠る
- 誰かと話す
- 病院に行くことを面倒がらない
そんな“あたりまえ”を積み重ねることが、百寿者たちの生き方に表れています。
一方で、普段病院で働いていると若くして亡くなってしまう方も多くいることを実感します。
長生きする人、若くして亡くなる人
両者の生き方に大きな違いはありません。
私の周りの方では、
・毎食乳製品を摂取することで100歳まで元気だった人
・毎日亜鉛を摂取することで健康に長生きした人
など、長生きの秘訣も人それぞれです。
みなさんも自分らしく生きて、健康に長生きできますように。
KOY
他ブログ記事:異例のインフルエンザ流行