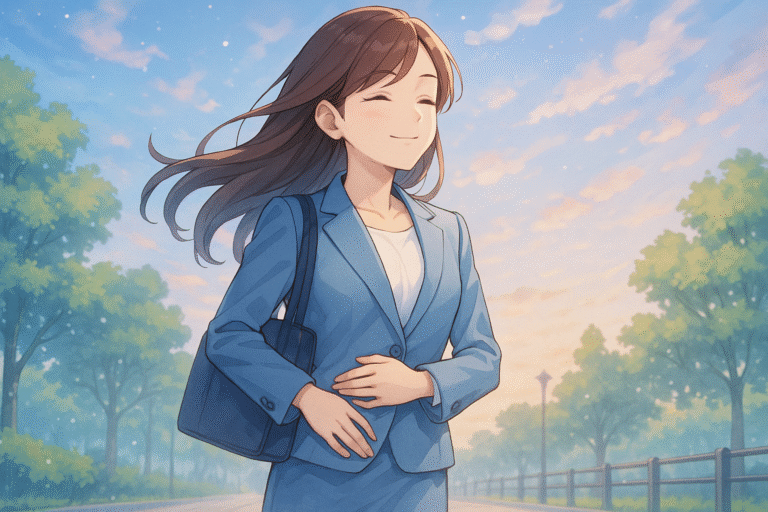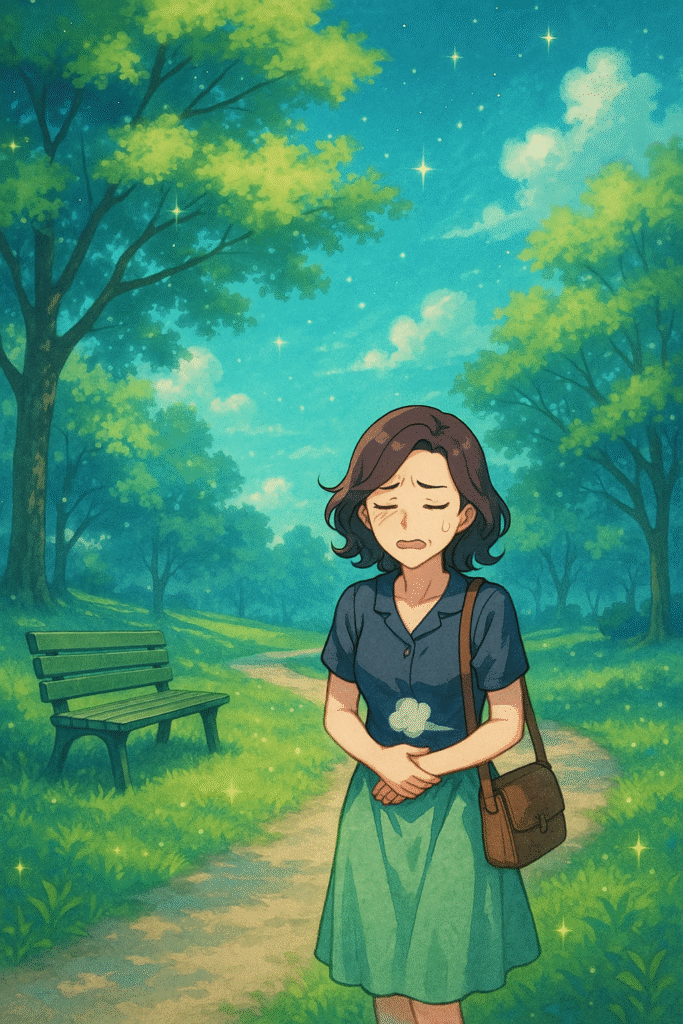
「先生、最近おならがよく出るんですけど…」
外来で診察をしていると、時々こんな相談を受けることがあります。
一見ちょっと恥ずかしい話題のように思えますが、実は“おならが増える”というのは、体の中で起きているちょっとした変化のサインかもしれません。
医師としての立場から言えば、ほとんどの場合は心配のいらない「生理的な現象」です。
でも、患者さんにとっては日常生活でのストレスや不安につながることもあり、決して軽くは扱えない問題です。
この記事では、
- そもそもおならって何なの?
- なぜガスがたまりやすくなるの?
- 病気のサインになることもあるの?
といった疑問に、消化器の専門医として医学的にわかりやすくお答えします。
「ちょっと気になるけど、病院で聞くのは恥ずかしい…」
そんな声にこたえる形で、おならの“正体”を紐解いていきます。
① おならって何?どこから来るの?
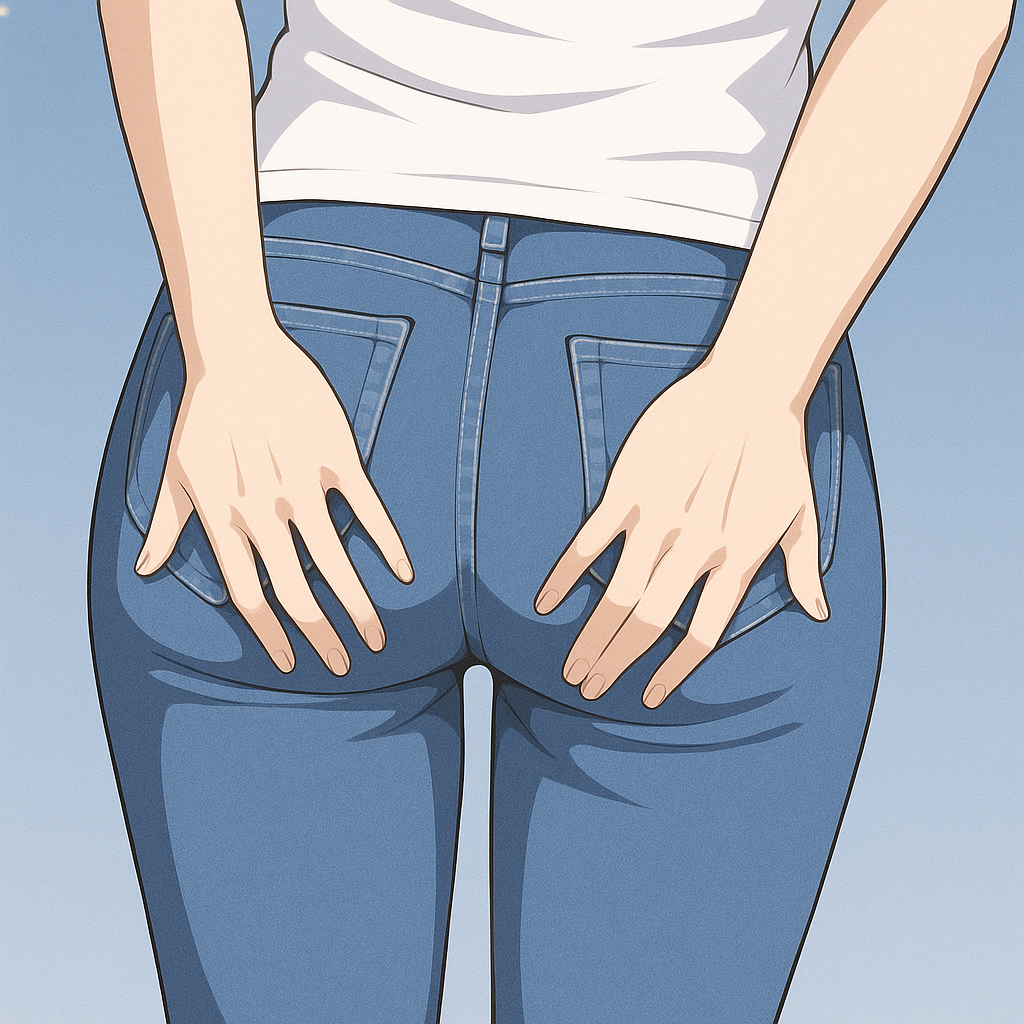
「おなら」とは、腸の中にたまったガスが肛門から外に出る現象のこと。
医学的には「腸管内ガス排出」とも呼ばれますが、要するに“腸がしゃべっている”ようなものです。
では、そのガスはいったいどこからやってくるのでしょうか?
実は、おならのガスには2つのルートがあります。
① 飲み込んだ空気(外から入ってくるガス)
私たちは食事中や会話中に、無意識に空気を飲み込んでいます。
この空気(主に窒素や酸素)は、胃を通って腸まで届き、最終的に“下から出る”こともあるのです。
・早食い
・炭酸飲料
・ガムや飴をよく噛む
こういった習慣は、空気を飲み込みやすくして「ガスが多くなる」原因になります。
② 腸内細菌が作るガス(体の中で発生するガス)
もうひとつは、腸内細菌が食べ物を分解するときに発生するガスです。
特に、食物繊維や糖質の一部(FODMAPと呼ばれる成分)を細菌が発酵させると、水素・メタン・二酸化炭素、そして時には**硫化水素(においの元)**などのガスが作られます。
つまり、おならは「食べたもの」と「腸内の細菌」のコラボレーションで生まれるものなのです。
おならは誰にでも出るもの。
1日に10回前後は“普通”とされており、多少の個人差があるのも当然です。
だから、「ちょっと多いかも…?」と思っても、まずは落ち着いて大丈夫。
でも、「いつもより多い」「臭いがきつくなった」「お腹が張る」など気になる変化があれば、それには理由があるかもしれません。
② おならが増える5つの原因

「最近、おならが多い気がする…」
そんなとき、実はいくつかの原因が考えられます。
ここでは、医学的におならが増える代表的な5つの理由を、わかりやすくご紹介します。
① 空気をたくさん飲み込んでいる(呑気症)
食事中や会話中に空気を一緒に飲み込むことを「嚥下性空気嚥下(えんげせいくうきえんげ)」といいます。
この空気がそのまま腸まで到達すると、おならとして出てくることがあります。
特に以下のような習慣がある方は要注意です:
- 食べるのが早い
- ガムや飴をよく噛む
- 飲み物をゴクゴク飲む
- 緊張しやすく、口呼吸や早口になりがち
- 炭酸飲料をよく飲む
これらの行動は、知らず知らずのうちに空気をお腹にためてしまうのです。
② 食べ物によるガス発生(発酵性の成分)
腸内細菌は、私たちが食べたものを“発酵”させてガスを発生させます。
特に以下のような食品は、おならの元となりやすいとされています:
- 豆類(大豆、納豆、豆腐など)
- イモ類(さつまいも、じゃがいも)
- キャベツ、玉ねぎ、ブロッコリーなどの野菜
- 果物(りんご、バナナなど)
- 小麦製品や乳製品
これらの食品は**腸内で分解されにくい糖質(FODMAP)**を多く含み、細菌のエサになってガスが増えやすくなります。
③ 腸内フローラ(腸内細菌のバランスの乱れ)
腸内には100兆個以上の細菌が住んでおり、そのバランス(腸内フローラ)が崩れると、ガスを多く作る菌が増えてしまうことがあります。
- 便秘が続いている
- 食生活が偏っている
- 抗生物質を使ったあと
こうした状態では「発酵ガス」が多く発生しやすくなり、においも強くなることがあります。
腸活や整腸剤などでバランスを整えることが大切です。
④ ストレスや過敏性腸症候群(IBS)
お腹の調子は心の状態とも密接につながっています。
ストレスや緊張、不安が続くと、腸の動きが不安定になり、「ガスがたまりやすい」「張る」「おならが頻繁に出る」といった症状につながります。
特に**過敏性腸症候群(IBS)**では、腹痛や下痢・便秘とともに「ガスが多い」と感じる人が多いのが特徴です。
⑤ 消化や吸収のトラブル(食物不耐症・SIBOなど)
- 乳糖不耐症:牛乳やヨーグルトなどの乳製品に含まれる「乳糖」をうまく消化できず、ガスや下痢の原因に。
- グルテン過敏症:小麦に含まれる「グルテン」でお腹が張ったりガスが出る。
- SIBO(小腸内細菌異常増殖症):本来は細菌の少ない小腸に菌が増え、食事後にガスが急激に増えることがあります。
これらは“体質”や“腸の環境”によるもので、気づかずに長年悩んでいる方も少なくありません。
✅まとめ
おならが増える背景には、生活習慣・食事・腸内環境・体質・ストレスなど、さまざまな要因が関係しています。
「最近多いかも…」と感じたら、思い当たる原因がないか、一度振り返ってみるのがおすすめです。
③ おならのにおいがきついときは?

「おならの回数も気になるけど、何よりにおいがキツくて…」
そんなお悩みを抱える方も少なくありません。
おならのにおいには、ちゃんとした“理由”があります。
この章では、おならのにおいが強くなる仕組みと、その対策について詳しくご紹介します。
🔸おならの“におい”の正体は?
実は、おならのほとんど(90%以上)は無臭のガスです。
- 窒素
- 二酸化炭素
- 水素
- メタン
など、においのない成分が大部分を占めています。
では、なぜ強烈なにおいを放つおならがあるのでしょうか?
その答えは――**「硫黄(いおう)を含むガス」**です。
🔸においの元になる“硫黄系ガス”
おならのにおいを決める主な成分には、以下のようなものがあります:
- 硫化水素(すいかすいそ):腐った卵のようなにおい
- メチルメルカプタン:キャベツが腐ったようなにおい
- ジメチルサルファイド:生ゴミのようなにおい
これらのガスは、主に腸内細菌が動物性タンパク質や含硫アミノ酸(メチオニンなど)を分解する過程で作られます。
🔸においが強くなる食べ物
においの強いおならが出やすい食事には、次のようなものがあります:
- 肉類(特に赤身の肉)
- 卵、チーズなどの動物性たんぱく質
- ニンニク、玉ねぎ、ネギ類(含硫化合物が豊富)
- **アルコール(特にビール)**も腸内発酵を促進することがあります
こうした食材を摂ると腸内の発酵が活発になり、においの強いガスが発生しやすくなります。
🔸腸内環境の乱れも関係あり
- 便秘があると、腸内に便が長くとどまり、発酵や腐敗が進んでにおいが強くなります。
- **腸内細菌のバランス(腸内フローラ)**が乱れていると、ガス産生菌や悪玉菌が増えてにおいが強くなることがあります。
- また、抗生物質の服用や不規則な生活・ストレスも腸内環境の乱れにつながります。
🔸においが急に強くなったら…?
「今までと違って明らかににおいがきつくなった」「ガスとともにお腹の張りや痛みもある」――
そんなときは、以下のような消化器系の病気が隠れている場合もあります。
- 便秘症・過敏性腸症候群(IBS)
- 小腸内細菌異常増殖症(SIBO)
- 胆のうやすい臓の異常(脂肪の消化不良)
- 大腸の疾患(大腸炎、ポリープなど)
「ちょっと様子がおかしいな」と思ったときは、無理せず一度医師に相談してみましょう。
✅まとめ:においにも“理由”がある
おならのにおいは、
- 食べたもの
- 腸内環境
- 体の調子
これらが複雑に関わって生まれる、いわば体からのサインです。
気になるにおいが続くときは、まずは食生活を見直し、それでも改善しないときは専門家に相談するのもありですね。
④ 今日からできる“おなら対策”

「においや回数が気になるけれど、病院に行くほどではない…」
そんなときに、自宅でできるおなら対策を知っておくと安心です。
ここでは、医学的に効果が期待できる5つのセルフケアを紹介します。
すぐに始められることばかりなので、ぜひ今日から意識してみてください。
① ゆっくり、よく噛んで食べる(=空気を飲まない)
早食いや“ながら食い”は、お腹に空気を多く取り込んでしまいます。
空気を飲み込みにくくするポイントは:
- 一口ごとにしっかり噛む(目安:20回以上)
- 食事中に会話しすぎない(話しながらだと空気を飲み込みやすい)
- 姿勢よく食べる(猫背は胃腸の動きを妨げます)
「よく噛むこと」は、消化を助けるだけでなく、ガスの発生を防ぐ第一歩でもあります。
② ガム・炭酸・ストロー飲みを控える
ガムを噛む、炭酸を飲む、ストローでジュースを吸う――
こうした行為も空気を飲み込みやすくなります。
- ガムや飴は控えめに
- 炭酸は1日1本までに
- ストローを使わず、コップで飲むようにする
ちょっとした工夫で、お腹に溜まる空気の量を減らすことができます。
③ 腸内環境を整える「腸活」を意識する
腸内の“菌のバランス”が整えば、ガスの発生は自然と減っていきます。
ポイントは、善玉菌を増やす食事を意識すること:
- 発酵食品:ヨーグルト、納豆、味噌、キムチなど
- 食物繊維(特に水溶性):わかめ・オクラ・バナナ・大麦など
- オリゴ糖:玉ねぎ、ゴボウ、バナナ、蜂蜜など
これらを毎日コツコツ摂ることで、腸内フローラが整い、ガスの発生を抑えられる可能性があります。
④ ストレスをためない・リラックス習慣をつくる
ストレスが腸に与える影響は大きく、腸の動きが乱れるとガスもたまりやすくなります。
- 深呼吸や軽い運動(ウォーキング、ヨガなど)
- お風呂でリラックス
- 睡眠をしっかりとる(腸の修復は夜間に活発化)
「気にしすぎること自体がストレス」になり、かえってお腹が張ることもあります。
“気楽に構えること”も立派なセルフケアのひとつです。
⑤ 食材を少しずつ調整してみる(FODMAPを意識)
食べ物によってガスの量が増える方は、「FODMAP(フォドマップ)」と呼ばれる特定の糖質を意識するとよい場合があります。
FODMAPが多く含まれる食品(=ガスが発生しやすい)
- 小麦製品(パン、うどん)
- 玉ねぎ、にんにく
- 牛乳、ヨーグルト(乳糖)
- りんご、梨、スイカ
FODMAPを完全に避ける必要はありませんが、「自分が反応しやすい食品」を知ることが大切です。
少しずつ量を減らしてみたり、食べるタイミングを調整するだけでも変化があるかもしれません。
✅まとめ:おなら対策は“生活の見直し”から
おならの回数やにおいが気になるとき、体からのサインと考えることはとても大切です。
「整腸剤を飲めば治る」という単純な話ではなく、
日々の食事・ストレス・腸の状態が複雑に関係しているため、少しずつ生活を整えることが根本的な対策につながります。
無理なくできることから、今日から1つずつ始めてみましょう!
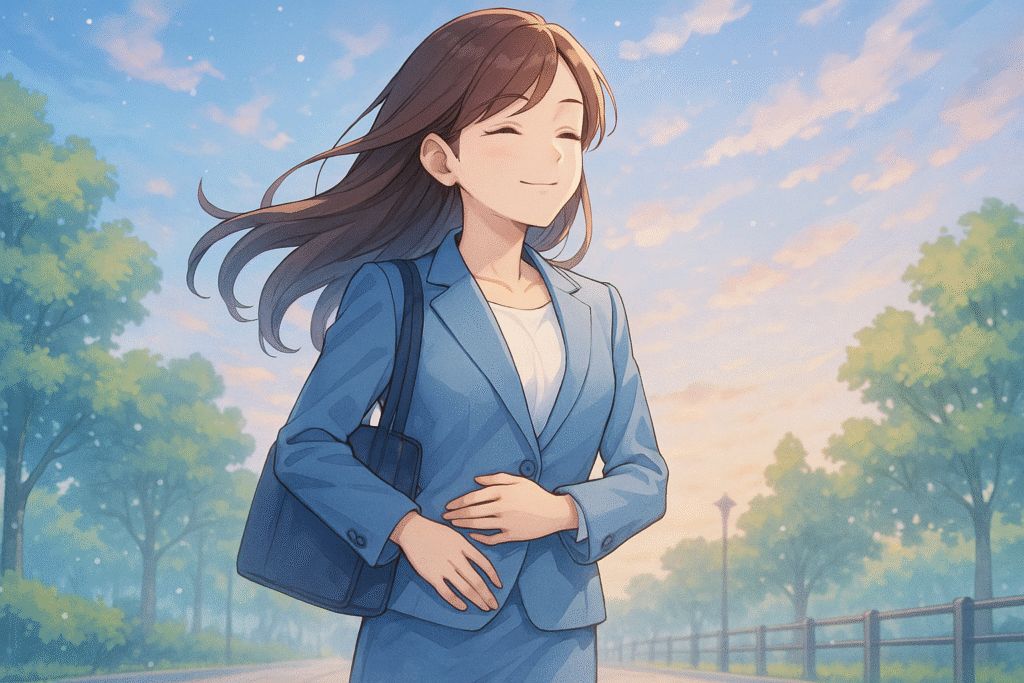
KOY
他サイト:大垣クリニック