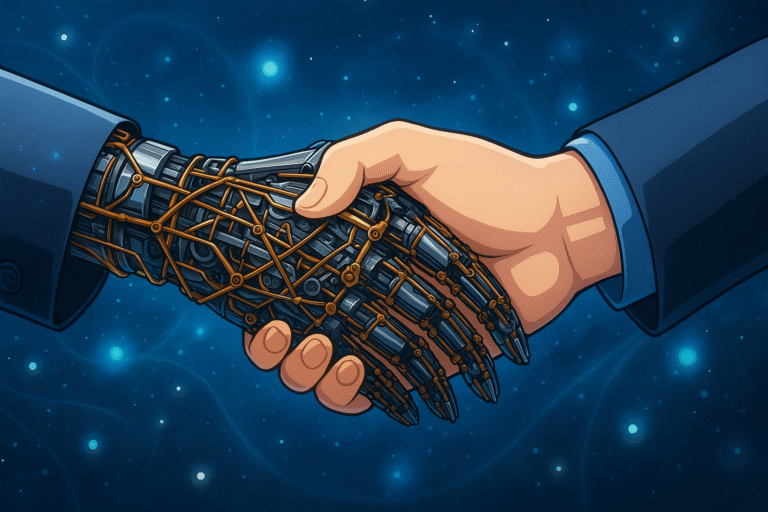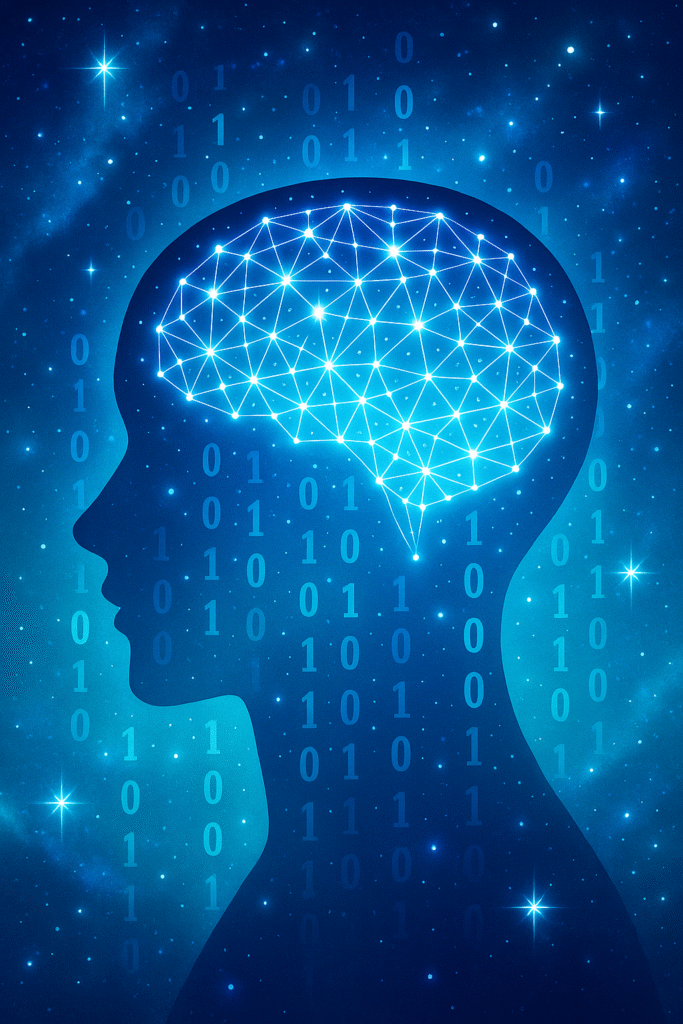
数年前までは「未来の話」だったAI(人工知能)が、今や私たちの暮らしのすぐそばに存在しています。
スマートフォンの音声アシスタント、AIによる文章生成、画像認識──そして、ついに医療の世界にもその足音がはっきりと聞こえるようになりました。
近年、AIを活用した診断支援ソフトや画像解析ツール、問診補助システムなどが次々と登場し、医療現場にも少しずつ浸透し始めています。
外科、内科、放射線科、病理診断…領域を問わず、**「AI導入を前提とした医療の形」**が模索される時代になりました。
しかしその一方で、現場にいる医療者としては、こう思うこともあるのではないでしょうか。
「本当に信頼できるの?」
「どこまで医師の仕事を任せられるの?」
「AIが医療を変えるって言うけど、実際のところ今どこまで進んでるの?」
このブログでは、そうした疑問に応えるべく、**医療現場へのAI導入の“今”**について、私なりの視点で整理してみたいと思います。
「AI=すごい」で終わらせるのではなく、医療者としてどんな可能性や課題があるのか、冷静に、そして柔軟に考えていくこと。
それが、テクノロジーとともに生きるこれからの医療に求められる姿勢かもしれません。
医療とAIが交わる時代へ
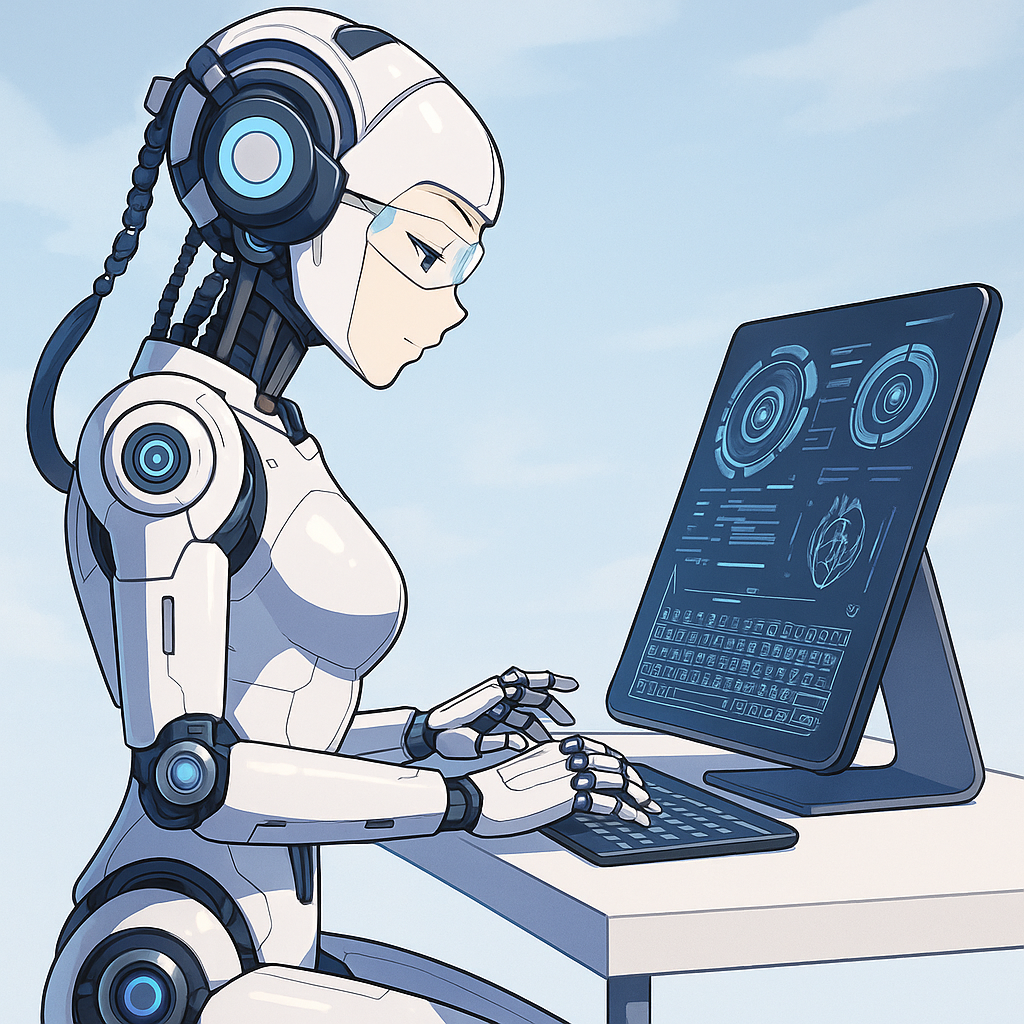
近年、AI(人工知能)の進化は目覚ましく、その波は医療の世界にも確実に押し寄せています。
特に2022年以降、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場は、
「AIと共に働く時代」の到来を現実のものとしました。
私たち医療者にとって、AIはもはやSFの話ではありません。
診療・研究・教育という三本柱のすべてにおいて、
AIの力を活用する場面が日々、増えてきています。
たとえば、臨床現場では
– AIによる問診補助や病名推定
– 画像診断支援(レントゲン・CT・MRIなど)
– 電子カルテの要約や文章作成の自動化
研究の場では
– 大量の論文を素早く読み込んで要約
– 統計解析のコード作成や仮説生成の補助
教育分野では
– 医学生や研修医向けの模擬診断シナリオの提供
– 複雑な医学知識をやさしく解説するツールとしての活用
このように、AIは多様な形で医療を支えはじめています。
しかしその一方で、
「どこまで任せてよいのか?」
「医師の役割はどう変わるのか?」といった疑問や戸惑いも、現場には確かに存在します。
この章では、そんな医療とAIが交わり始めた今という時代の空気感を、
現役医師の視点から少し俯瞰して眺めてみたいと思います。
実際に私の周りでも多くの医師が生成AIを使用しています。
現時点では個人的に使っているのみで、まだ実際の臨床の場で応用して使われている印象はありません
日進月歩の世の中であり、近い将来AIがより使われてくることは間違いないと感じています。
医療におけるAI導入のリアル
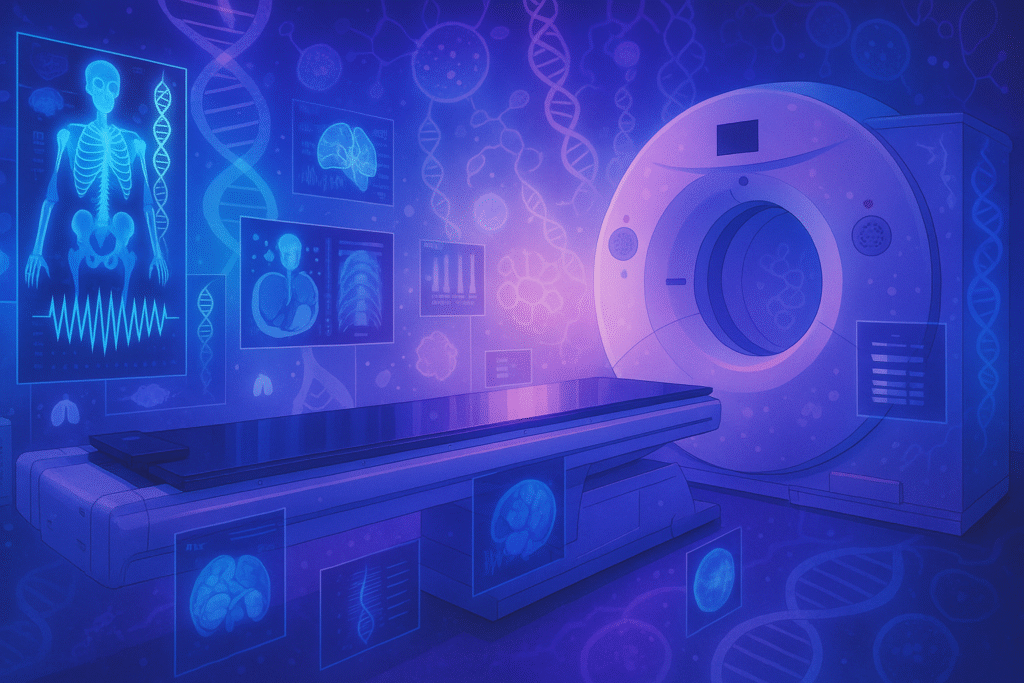
1. 画像診断支援(放射線科・病理・皮膚科など)
- 放射線画像の自動解析:頭部CTや胸部X線、乳がん・肺がんの検出をAIで補助。米国では340以上のAI画像診断ツールがFDA承認され、米放射線科の約2/3が導入済みです
The Washington Post - 病理画像解析(デジタル病理):乳がんや胃がん・大腸がんなどの病理組織像をAIで解析し、診断支援を実施。欧州や米国で臨床導入が進んでいます
ウィキペディウィキペディア - 皮膚科画像診断:皮膚癌や悪性黒色腫の写真をAIで解析。臨床試験では、医師レベルの精度を示す結果も出ています
ウィキペディア
2. 心電図・心エコー解析(循環器)
- 心電図(ECG)解析による心疾患スクリーニング:Columbia大学で開発されたEchoNextは、ECGから構造的心疾患(SHD)を77%の精度で検出、臨床試験中
ニューヨークポスト - 心エコーの自動評価:AIが心エコーデータを解析し、心機能の定量評価や疾患のスクリーニングを支援する製品も臨床的に実用化が進んでいます
ウィキペディア
3. 内視鏡・消化器領域
- 胃がん・大腸がんの検出支援:AIによる内視鏡画像解析で病変の早期発見を補助。感度が専門医と悪くないと報告されたケースもあり、実用化が進行中
ウィキペディ
4. 電子カルテや問診AI、自動レポート作成
- 診察記録の自動要約・文章生成:ChatGPTなどの生成系AIを活用し、問診内容の要約、自動カルテ記入、紹介状・同意書の下書きなどが実験的に利用されています(FDAリストにも多数含まれます)
U.S. Food and Drug AdministrationU.S. Food and Drug Administration - 臨床意思決定支援システム(CDSS):「CarePre」などはEHRデータを用いて今後の診断や治療イベントを予測し、医師の判断をサポート
arXiv
📁参考・信頼情報源(HP/論文等)
- FDAのAI/ML医療機器リスト(承認済ツール一覧) U.S. Food and Drug Administration+1U.S. Food and Drug Administration+1
- Aidoc:FDA承認のCT画像AI(脳・肺血栓等)ウィキペディア
- Derm:NHS採用の皮膚癌AI<br>ザ・タイムズ
- EchoNext:ECGから心疾患検出77%精度 ニューヨークポスト
- 学術レビュー:病理・皮膚・循環器・消化器AI導入例 ウィキペディア
- CarePre:臨床予測モデルを活用したCDSS arXiv
🔎まとめ
- 多領域で実用化が進んでおり、FDA/NHS承認済のAIツールが実際に診療で使われている
- 放射線・病理・皮膚・消化器・循環器など幅広い分野
- 現在のAIは“補助ツール”が主流。医師との協働が前提
- 生成系AIは記録や問診補助などで検証が進行中
医師の役割はどう変わるのか?
―― 裁量・判断・患者との関係性にフォーカスして
AIの進化により、医師がこれまで担ってきた業務の一部が、確実に代替されつつあります。
しかしそれは、医師の“存在意義”が失われるということではありません。むしろ、「医師にしかできないこと」が明確になっていくプロセスでもあります。
たとえばAIは、画像診断において病変の検出やスクリーニングではすでに高い精度を誇ります。問診やカルテ要約などの“情報整理”の場面でも、ChatGPTのような生成系AIは有用です。
ですが、最終的に治療方針を決定する「裁量」や、複雑な症状・背景を踏まえた「判断」は、いまだ人間の医師に委ねられています。
さらに見逃してはならないのが、患者との関係性の構築です。
患者は診断名だけを知りたいのではなく、「この症状が自分にどう影響するのか」「どう向き合っていけばいいのか」という心の部分への寄り添いを求めています。これは、AIには難しい領域です。
つまり、これからの医師には
- AIでは補えない「人間力」(共感力、傾聴力)
- 「判断・責任を負う力」(倫理、全体を見通す力)
- AIを使いこなすスキル(デジタルリテラシー、批判的思考)
といった資質がますます重要になってきます。
AIに業務を「奪われる」のではなく、AIと協働して価値ある仕事を創り出す。
そんな意識の変化が、これからの医療者には求められているのかもしれません。
課題と懸念:AIが万能ではない理由
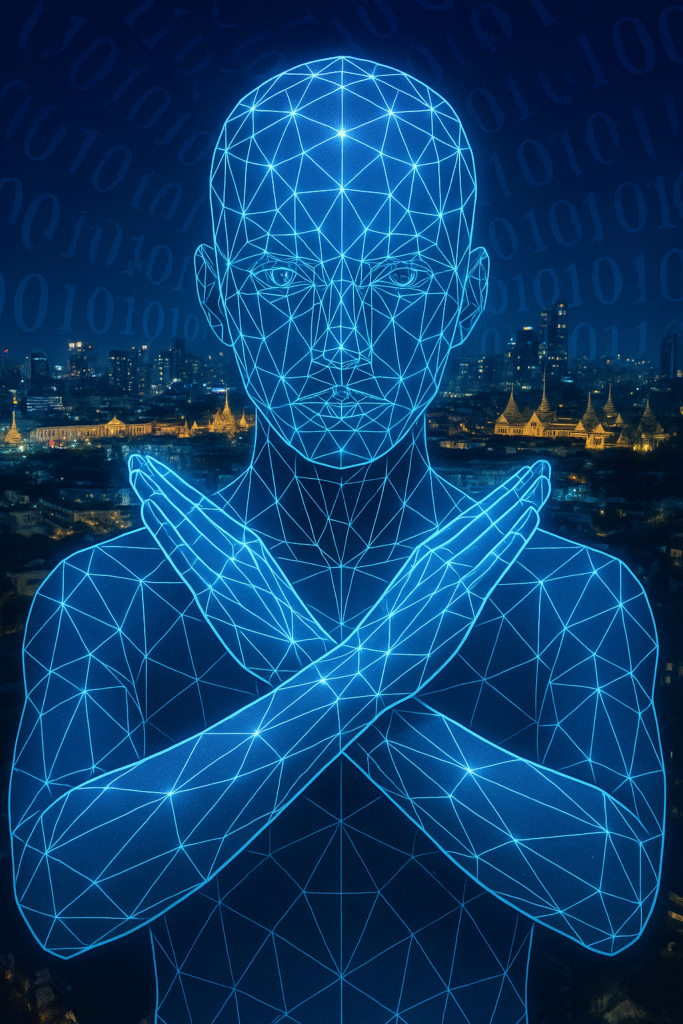
医療にAIが導入されることで、効率化や精度の向上が期待される一方で、現場にはさまざまな課題や懸念も残されています。
AIは決して“万能の存在”ではありません。その限界を理解し、適切に使うことが、むしろ医療の質を高める鍵となるのです。
1. 学習データの偏りと限界
AIは膨大なデータをもとに学習しますが、その“データの質”がAIの判断精度を左右します。
もし学習に使われた症例データが特定の地域や人種、年齢に偏っていれば、それはそのまま診断精度のバイアスとなり、誤診や見落としにつながる恐れがあります。
2. 説明責任の所在が曖昧
AIが出した診断や治療提案に対して、「なぜそう判断したのか?」という説明ができないことがあります(これを“ブラックボックス問題”と呼びます)。
患者や家族に説明する責任がある医師にとって、根拠を可視化できないAIの判断は扱いが難しく、トラブルの火種にもなり得ます。
3. 倫理的・法的な整備が追いついていない
AIによる医療ミスが起きたとき、「責任は誰が負うのか?」という法的な整理はまだ不十分です。
さらに、患者の個人情報をAIにどこまで預けてよいのか、どのようにデータを保護するのかといった倫理的課題も未解決のままです。
4. 現場とのギャップ
AIツールが現場に導入されても、操作が複雑だったり、医療現場のワークフローに合わなかったりして「使われないAI」となってしまう例もあります。
結局、使いこなせる医師が限られ、格差を広げる要因になってしまう可能性も否定できません。
これからの医療者に求められる視点とは

――「AIを使いこなす」スキルと倫理観
AIが医療現場に入り込んできた今、私たち医療者に求められるのは、もはや「AIに慣れる」ことではなく、「AIを活かす」ことです。
1. AIを“道具”として正しく使うスキル
AIを使いこなす医療者には、最低限のデジタルリテラシーが求められます。
たとえば、AIが出力した診断候補を「うのみにする」のではなく、「この結果は妥当か?根拠は?補足すべき情報は?」といった**批判的思考(クリティカル・シンキング)**が重要です。
さらに、AIの仕組みや限界について基本的な理解を持っておくことで、「AIと医師の連携」をうまく設計できるようになります。
2. 患者中心の医療を貫く姿勢
AIがどれだけ正確な診断を出せたとしても、それを患者にどう伝え、どう治療を進めるかは医師の役割です。
患者の価値観や生活背景に寄り添い、対話を重ねる“人間らしさ”が、今後ますます重視されるでしょう。
3. 倫理観と責任感
AIを活用する上で、プライバシー保護やデータ利用のルールに対する理解と責任感も欠かせません。
「何ができるか」だけでなく、「それをすべきか?」という倫理的判断が必要な時代に入っています。
最後に・・・
最後までブログ記事を読んでいただいてありがとうございました。
今後、生成AIが私たち医療の中に食い込んでくることは間違いないと思いますし、
近い将来そうなるかもしれません。
現時点では、かなり便利なツールとしての使用のみで、それ以上の存在ではないという印象です。
私も、生成AIを患者様の個人情報に気をつけながら、今後使ってみて、どんどんブラッシュアップしていければと考えております。
より良い医療にするために、生成AIと医師がうまくコラボレーションして、スムーズな医療が実現できれば最高です。
今はそのような状況であり、変わらず医師が責任を持って患者さんに接するという姿勢は変わりないと思います。
今後も生成AIに注目していきましょう。 ありがとうございました。
KOY
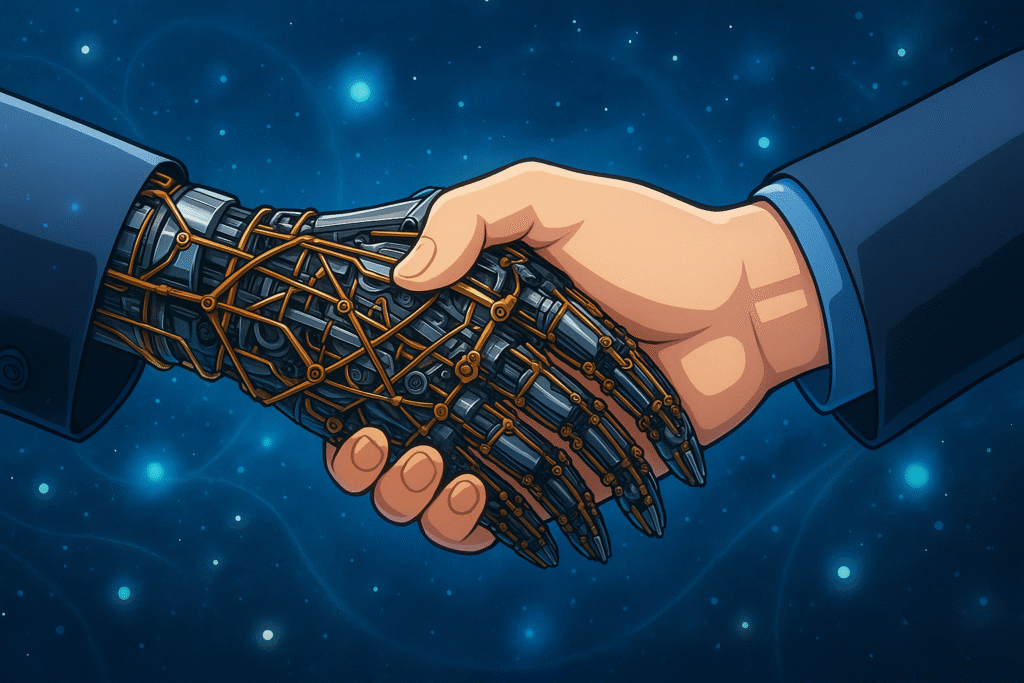
当ブログ他記事:アナフィラキシー・ハチ刺され、チョクビ(直美)