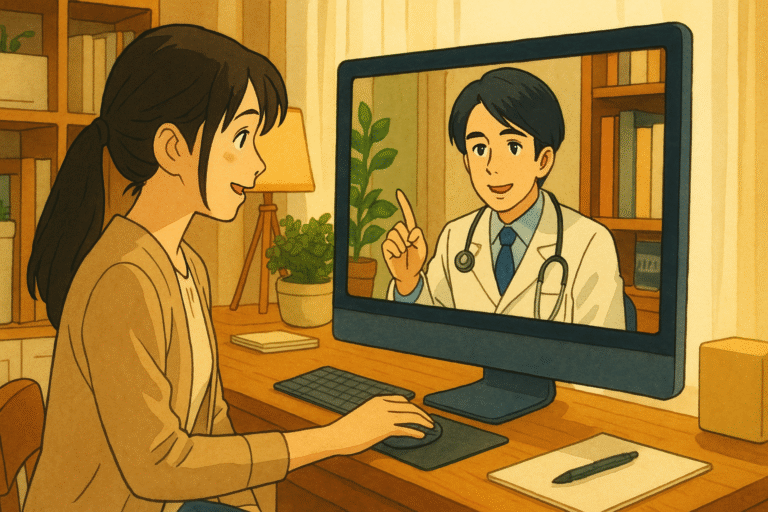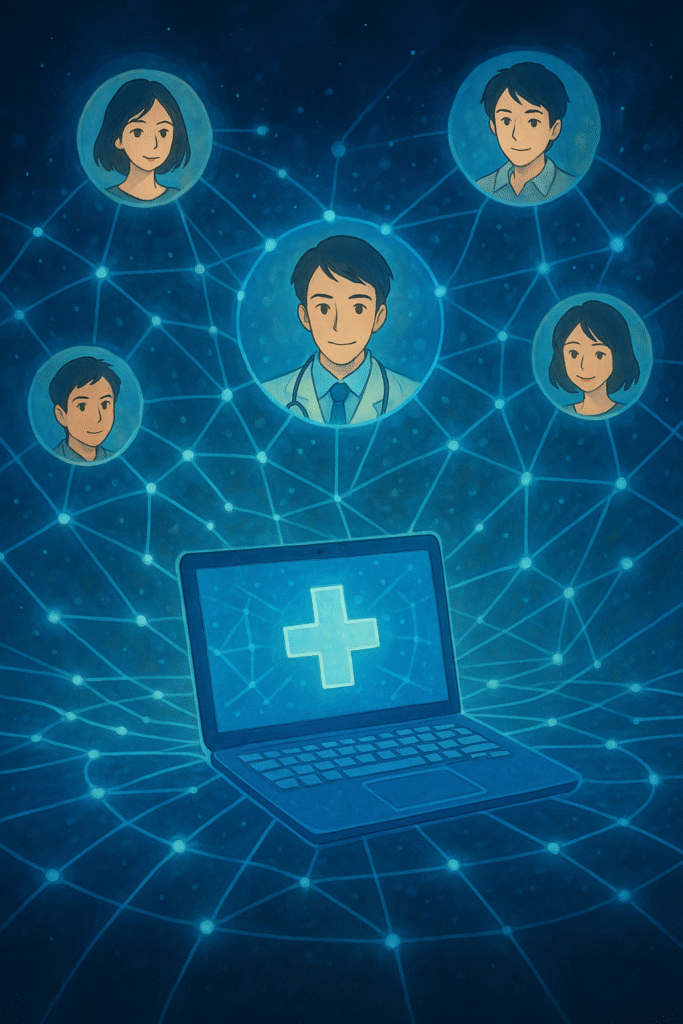
「病院に行くのは待ち時間が長いし、仕事や家事でなかなか時間が取れない…」
そんな悩みを持ったことはありませんか?
最近、スマホやパソコンを使って自宅にいながら医師の診察を受けられる “オンライン診療” が広がっています。
診察から薬の処方までを自宅で完結できるケースもあり、特に忙しい社会人や子育て世代、高齢の方にとっても便利な仕組みです。
一方で、「本当にちゃんと診てもらえるの?」「対面とどう違うの?」と不安に思う方も少なくありません。
この記事では、オンライン診療の基本からメリット・デメリット、実際の流れまで解説します。


オンライン診療とは?
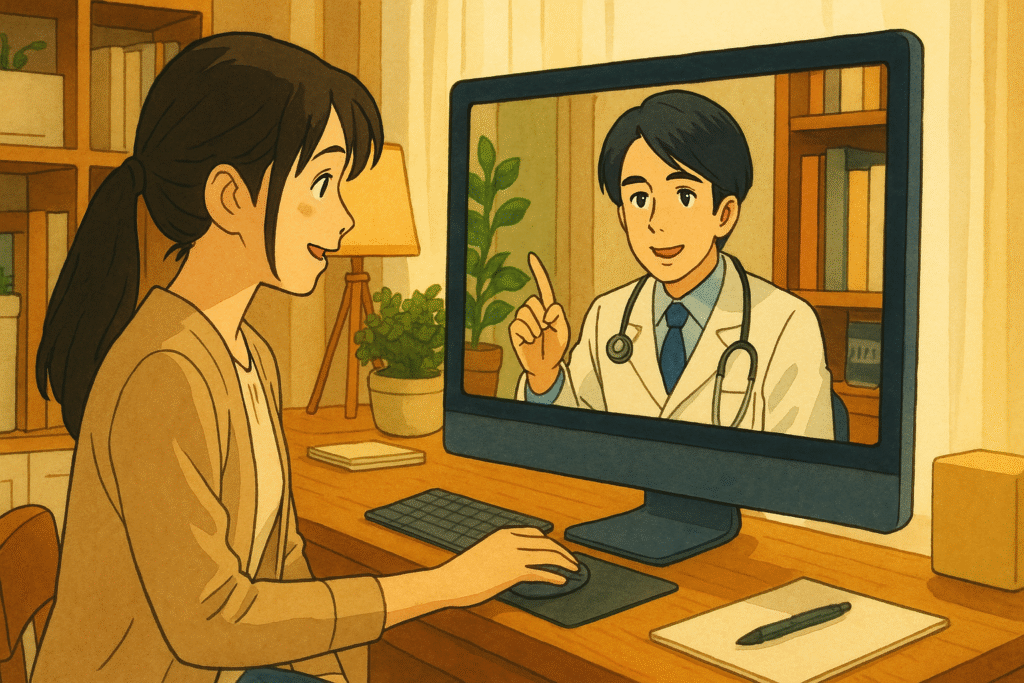
オンライン診療とは、スマホやパソコンなどを使って、医師とビデオ通話で診察を受けられる仕組み のことです。
厚生労働省も制度として認めており、2018年から本格的に導入され、コロナ禍をきっかけに急速に広まりました。
従来の「対面診療」と大きく違うのは、病院やクリニックに行かなくても医師とつながれる という点です。診察の後には薬の処方も可能で、薬局で受け取ったり、自宅に配送してもらえるサービスもあります。
実際の診療の形式
オンライン診療は、専用アプリやWebサービスを通じて行われます。基本的な流れは次のとおりです。
- 予約:スマホやパソコンから診察予約をする
- 問診:アプリ上で症状や既往歴を入力する
- 診察:予約時間になったら、ビデオ通話で医師と対面。カメラを通して患部を見せることも可能
- 処方:必要に応じて処方箋が発行され、薬局で受け取り、または配送で自宅に届く
つまり、実際の診療は「テレビ電話の診察版」といったイメージです。
対象となるのは、例えば以下のようなケースです。
- 生活習慣病(高血圧、糖尿病など)の定期的な診察
- 花粉症やアトピーなどのアレルギー疾患
- 皮膚トラブル(ニキビ、湿疹など)
- メンタルヘルス(うつ、不眠などの相談)
- 感染症流行期の発熱外来(条件つき)
ただし、すべての病気に適しているわけではなく、検査や処置が必要な場合は対面診療が必須 になります。
そのため、オンライン診療は「ちょっと相談したい」「継続的に薬をもらいたい」など、軽症・慢性疾患に向いていると言えるでしょう。

オンライン診療のメリット
オンライン診療には、日常生活をラクにしてくれる魅力がたくさんあります。
- 通院時間・待ち時間がゼロ
病院までの移動や待合室での待ち時間がなく、自宅や職場からそのまま診察を受けられます。忙しい社会人や子育て中の方にとって大きなメリットです。 - 感染症リスクの回避
病院に行かないため、インフルエンザや新型コロナなどの感染症にかかるリスクを減らせます。特に高齢者や基礎疾患を持つ方には安心です。 - 遠方でも専門医にアクセス可能
地域によっては専門医が少ないこともありますが、オンラインなら距離を気にせず受診できます。地方在住の方や移動が難しい方にとって心強い仕組みです。 - 薬の宅配サービスと組み合わせれば完結
診察から処方箋発行、薬の受け取りまでを自宅で完結できる場合があります。体調が悪いときでも外出せずに済むのは大きな利点です。

デメリット・注意点
一方で、オンライン診療にも限界や注意点があります。利用前に知っておくと安心です。
- 初診は対面が必要なケースが多い
日本の制度では、原則として初めての診察は対面で行う必要があります(例外は一部あり)。再診からオンラインを利用する形が一般的です。 - 検査や処置は当然できない
血液検査やレントゲン、注射や処置などはオンラインでは不可能です。必要に応じて病院に行くことになります。 - 病状によっては適さない
緊急性の高い症状や重い病気はオンラインでは対応できません。例えば「強い胸の痛み」「激しい腹痛」などは迷わず救急外来を受診すべきです。 - 通信環境や操作スキルが必要
スマホやパソコンの操作、安定したインターネット環境が前提となります。通信が不安定だと診察がスムーズに進まないこともあります。

オンライン診療のメリット・デメリット
| メリット ✅ | デメリット ⚠️ |
|---|---|
| 通院時間・待ち時間がゼロ | 初診は対面が必要なケースが多い |
| 感染症リスクの回避 | 検査や処置はできない |
| 遠方でも専門医にアクセス可能 | 病状によっては適さない |
| 薬の宅配サービスと組み合わせれば完結 | 通信環境や操作スキルが必要 |

今後の展望
オンライン診療はまだ始まったばかりの仕組みで、これからさらに進化していくと考えられています。
まず注目されているのが、AI(人工知能)との組み合わせです。
症状を入力するとAIが自動で症状チェックやトリアージ(緊急度の判定)を行い、その情報をもとに医師が効率よく診察できるようになる可能性があります。
これにより、診療の質が高まり、医師の負担軽減にもつながります。
また、高齢化社会での医療アクセス改善にも期待されています。
移動が大変な高齢者や介護を受けている方が、自宅から診察を受けられるようになれば、医療の継続性を保ちやすくなります。
さらに、医療格差の解消も重要なポイントです。
都市部に集中しがちな専門医療を、地方や離島の患者さんにも届けられるようになれば、日本全体の医療水準を底上げすることにつながります。
ただし、法制度やセキュリティ、診療の質をどう担保するかといった課題も残されています。
これらを解決しながら、オンライン診療は「対面診療を補う新しい医療の形」としてますます身近になっていくでしょう。
今後の展望(まとめ表)
| 展望 | 内容 |
|---|---|
| AIとの連携 | 症状チェックやトリアージをAIが補助し、診療の効率化・質の向上をサポート |
| 高齢化社会での活用 | 移動が難しい高齢者や介護中の方が、自宅から診察を受けやすくなる |
| 医療格差の解消 | 都市部に集中する専門医療を、地方や離島の患者さんにも提供できる |
| 課題の克服 | 法制度・セキュリティ・診療の質の確保といった問題を解決する必要あり |

実際にあったトラブルまとめ
オンライン診療で報告されている主なトラブル例
| 種類 | 内容・事例 | 問題点・注意すべき点 |
|---|---|---|
| 不適切な処方・過剰処方 | 痩身目的(ダイエット)を謳って、糖尿病治療薬(GLP-1受容体作動薬など)が処方された事例が報告されている。 国消センター | 本来の適応外の使用。副作用リスクがある。初診で処方日数や判断が不十分なまま処方されるケースも。 国消センター |
| 説明不足・同意不足 | 副作用や相互作用の説明が不十分、解約条件や契約条件(継続課金など)が明確でない、あるいは後から解約困難という訴えがある。 郡山市公式サイト | 患者側が十分なインフォームド・コンセントを得ていないこと。トラブル時の責任が曖昧になるリスク。 |
| 契約・解約トラブル | 定期購入型になっており、途中解約ができない、返金不可といった対応を受けたという相談も。 郡山市公式サイト | 特定商取引法の扱いとのずれ、契約方式・申込方式の説明不備。 |
| 責任・責務の不明確さ | オンライン診療サイトの運営者と実際に医師を提供する医療機関との責任分界が分かりにくく、トラブル時に「誰に問い合わせればいいか」が曖昧になるケース。 国消センター | 患者が混乱。医療機関・運営者双方が説明責任を果たしていない可能性。 |
| 診断ミス・見逃し | オンラインでは触診・聴診・画像検査ができないため、所見を取り違えたり、重症疾患を見逃す危険性が指摘されている。 東京医師会 | オンライン診療の限界として、適応を誤る、重篤な所見を取りこぼすリスク。 |
| 通信・操作トラブル | 通信環境が悪く、音声・映像が途切れたり、操作画面でトラブルが起こって診察が進まないケース。 東京医師会 | 患者・医師双方で通信安定性や機器操作が不可欠。高齢者など操作に慣れない層にはハードルになる。 |
| プライバシー・セキュリティ | 個人情報や医療データの取り扱い・通信の暗号化などが不十分で、情報漏えいなどを懸念する声。 東京医師会 | 医療情報は高度な守秘義務が伴うため、システム設計・運用の安全性が求められる。 |
実際の事例(具体例)
- 国民生活センターには、痩身目的のオンライン診療で「基礎疾患の問診を十分にせずに処方された」「副作用が出たが解約できない」といった相談件数が増加していると報告されています。
CareNet.com - 郡山市消費生活センターの例では、不妊治療を標榜するオンラインクリニックで月額契約を申し込んだら、糖尿病薬が送られ、「2回目以降は中断できるが解約できない」と説明された事例があります。
郡山市公式サイト - 自由診療(保険適用外の診療)での事例として、オンラインで広告により「GLP-1ダイエット」として適応外使用の処方を行った医療機関が、日本医師会などから懸念を表明されたことがあります。
日本医師会

まとめ
オンライン診療は、忙しい毎日を送る人や病院に通うのが難しい人にとって、とても心強い医療の新しい形です。
通院や待ち時間を減らし、感染症リスクを避けながら診察を受けられるという大きなメリットがあります。
一方で、検査や処置が必要な場合には対応できないなど、限界や注意点も存在します。
トラブル事例も報告されていますので、「オンラインでできること・できないこと」を理解して、しっかりコミュニケーションを取って上手に活用することが大切です。
これからはAIとの連携や制度の整備が進み、さらに利用しやすく、安心できる仕組みになっていくでしょう。
オンライン診療は万能ではありませんが、対面診療と組み合わせて賢く使うことで、私たちの健康を支える大きな味方になるはずです。
KOY
当ブログ記事:トランプ関税/医薬品、インフルエンザ/ワクチン