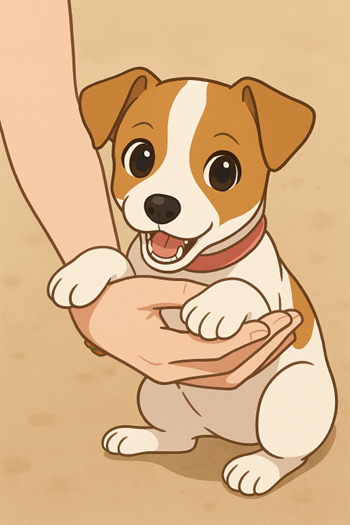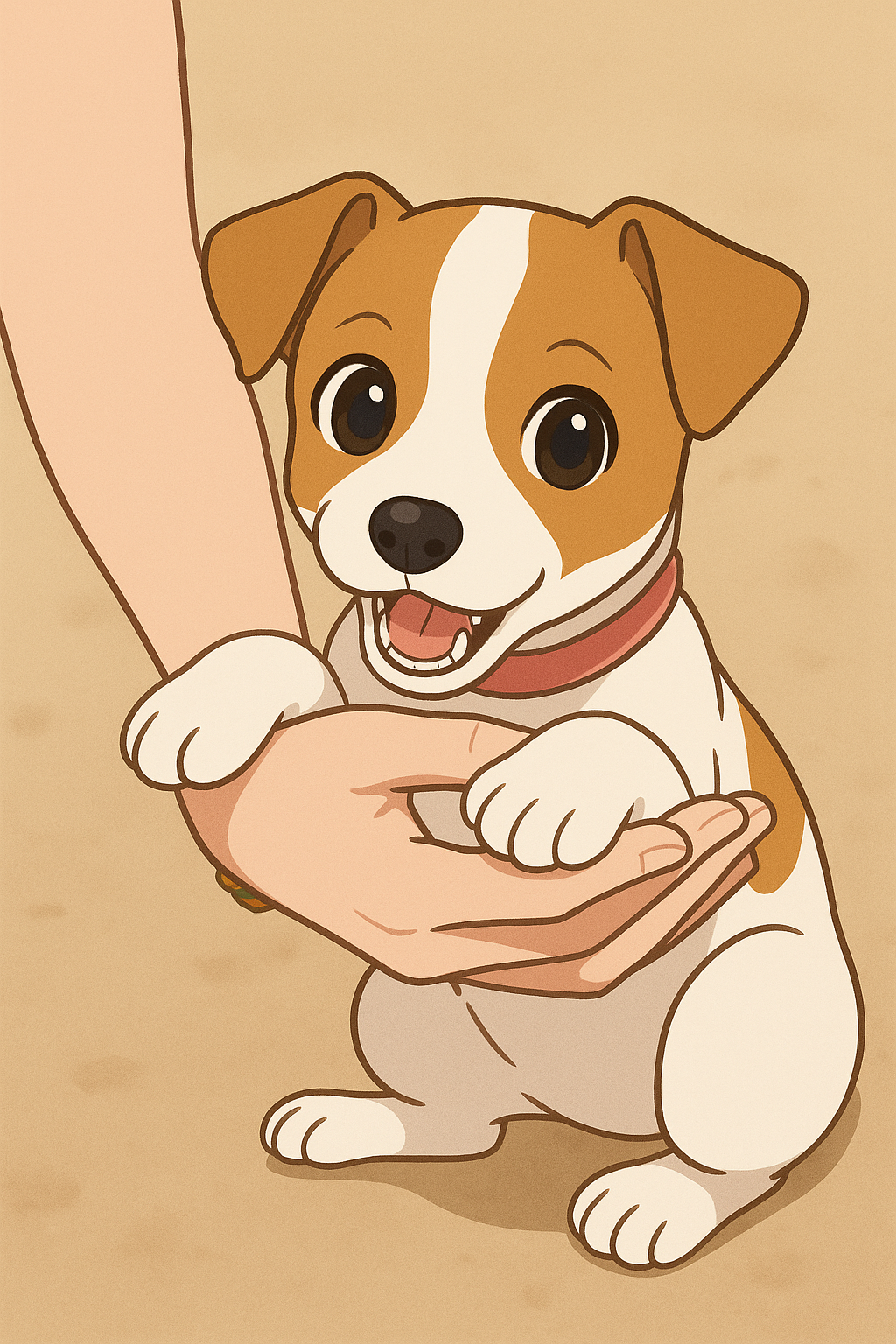「うちの犬に、ちょっと手を噛まれちゃって…」
「さっき猫を抱っこしてたら、ガブッとやられました」
こんな経験、ありませんか?
犬や猫に噛まれるのは、ペットと暮らしている人にとって珍しいことではありません。
中には「甘噛みだし、たいしたことないかな」と思って様子を見てしまう人も多いのではないでしょうか。
ですが実は――
動物に噛まれた傷は、意外なほど深刻な感染症につながることがあります。
傷が小さくても油断は禁物。特に猫に噛まれた場合、傷口が小さく目立たないぶん、気づいたときには赤く腫れ上がっていた…というケースも少なくありません。
このブログでは、犬や猫に噛まれたときの正しい対処法と、
病院を受診すべきサインについて解説します。
動物に噛まれるとこんなリスクが!
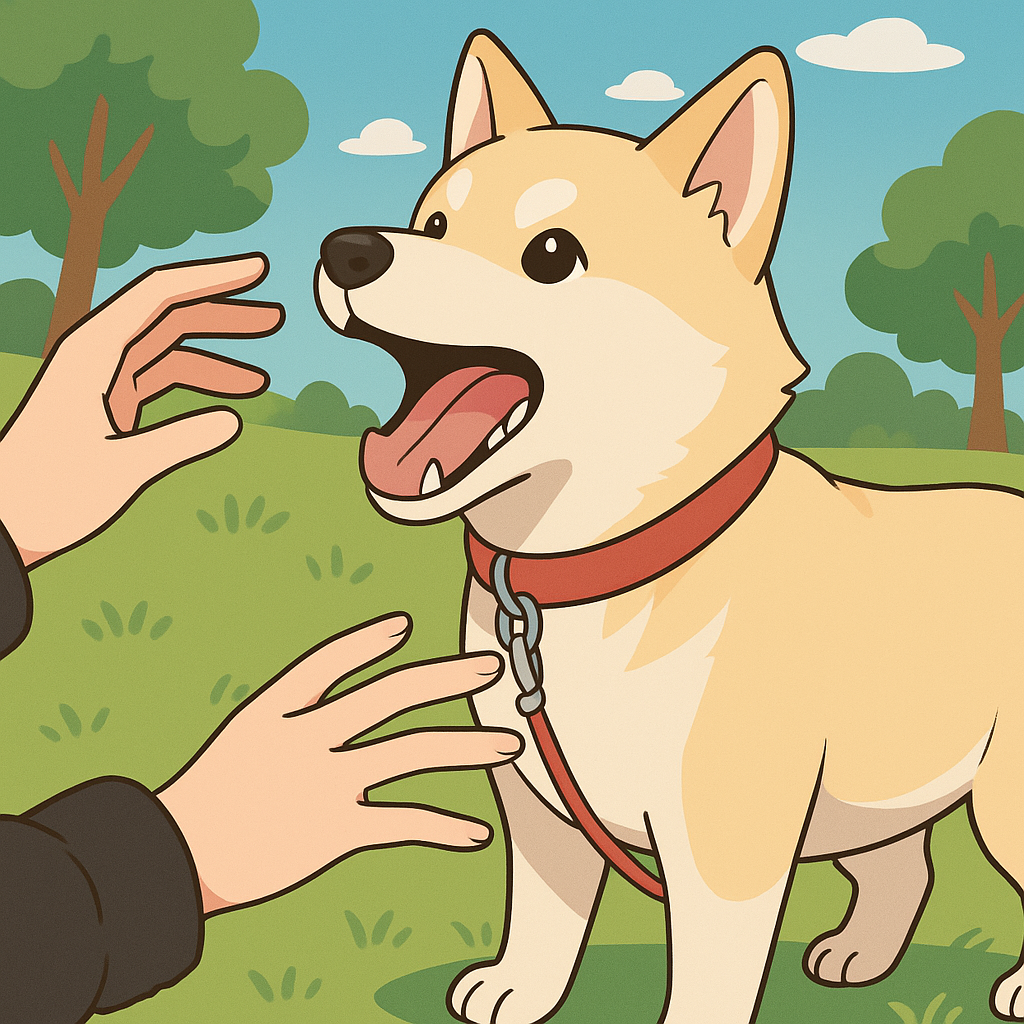
動物に噛まれた傷は、「見た目以上に危険」です。
なぜなら、動物の口の中にはたくさんの細菌がひそんでいて、それが傷口から体内に入り込むからです。
特に、犬や猫に噛まれた場合、次のような感染症のリスクがあります。
🔬1. パスツレラ感染症(Pasteurella)
犬や猫の口腔内に常在する細菌で、咬傷後に最もよく見られる感染症のひとつです。
数時間〜1日以内に、傷口の周囲が赤く腫れて痛み、膿が出ることもあります。
ひどくなると発熱やリンパ節の腫れが起き、抗菌薬の内服や点滴が必要になることも。
🦠2. カプノサイトファーガ感染症(Capnocytophaga)
少し聞き慣れない名前かもしれませんが、特に高齢者や糖尿病、がん治療中など免疫力が低下している人では注意が必要です。
発症すると、敗血症や髄膜炎などの重篤な合併症を起こすことがあり、死亡例も報告されています。
💉3. 破傷風(Tetanus)
土の中にいる菌として有名ですが、動物の唾液を介して感染することも。
破傷風菌は神経に作用し、筋肉のこわばりやけいれんを引き起こす非常に危険な病気です。
咬傷を受けた場合、ワクチン接種歴が不明なら追加接種が必要になることもあります。
当ブログ記事:破傷風ワクチン
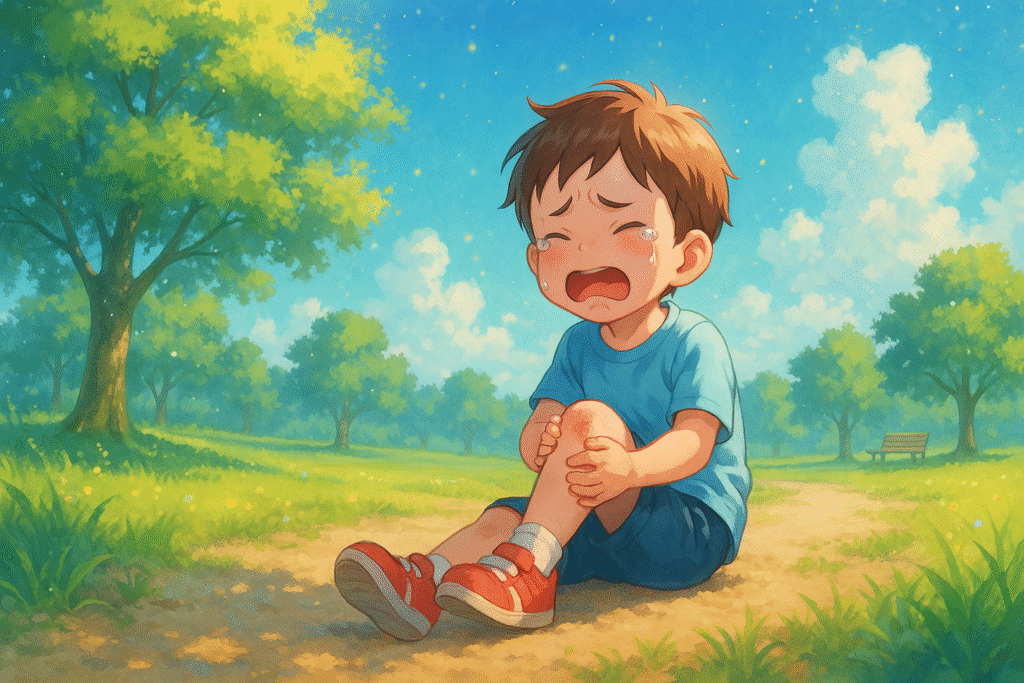
🐕🦺4. 狂犬病(Rabies)※海外で特に注意!
日本では犬のワクチン接種制度が徹底されており、国内の発症は極めて稀ですが、海外で犬や猫に噛まれた場合は要注意。
狂犬病は一度発症すると**致死率ほぼ100%**の恐ろしい感染症です。
海外旅行中に動物に噛まれたら、すぐに現地の医療機関を受診してください。
🧠見た目は小さくても油断しないで!
特に猫の咬傷は、針で刺したような細い傷になりやすく、見た目では深さがわかりにくいため注意が必要です。
表面がすぐにふさがってしまうことで、内部に閉じ込められた菌が増殖し、数日後に腫れや発熱が出ることもよくあります。
また、手や指を噛まれた場合は腱や関節に感染が広がりやすく、最悪の場合、手術が必要になることも。
少しでも異変を感じたら、早めに医療機関を受診することが大切です。
噛まれた直後にすべき応急処置

「ちょっと歯が当たっただけだから…」と、つい軽く見てしまいがちな動物の咬み傷。
ですが、感染リスクを下げるためには**“その場ですぐ”の対応がとても重要です。
ここでは、犬や猫に噛まれたときに自宅でできる応急処置の手順**をご紹介します。
✅ 1. まずは“流水”でしっかり洗い流す!
噛まれたら、すぐに流水で5〜10分間、しっかりと傷口を洗い流すことが大切です。
水圧で口の中の細菌や汚れを物理的に洗い流すことが、感染予防の第一歩になります。
- 蛇口の水でもOK(勢いがあるとより効果的)
- 傷が深くても、洗い流すのが優先
- 出血していても、軽く押さえながら洗浄を継続
※「傷が開くのが心配」と思っても、この時点では洗浄が最優先です。
✅ 2. 石けんで周囲の皮膚をやさしく洗う
流水で洗ったあとは、周囲の皮膚を石けんでやさしく洗浄します。
ただし、傷口の中までは石けんを入れないよう注意してください。無理しなくで大丈夫です。
- 殺菌作用のある石けんが理想(なければ普通のものでOK)
- 傷にしみる場合は無理にこすらない
✅ 3. 清潔なタオルやガーゼで止血
出血している場合は、清潔なガーゼやタオルで圧迫止血を行います。
強く押さえすぎると逆に組織を傷めることもあるので、じんわり圧をかけるのがポイントです。
基本的に噛まれた傷の出血で大事になることはほぼありません。
辛抱強く、落ち着いて圧迫し続けてください。
✅ 4. 消毒液の使用は慎重に
最近では「消毒しない方が治りが早い」とも言われますが、咬傷の場合は細菌感染のリスクが高いため、軽く消毒しておくのも一つの方法です。
- ポビドンヨード(イソジン)やクロルヘキシジンなどが使われることが多い
- アルコール消毒は刺激が強すぎておすすめしません
✅ 5. そのあとはすぐに医療機関へ!
応急処置が済んだら、できるだけ早く病院を受診しましょう。
「小さな傷だから」と自己判断で様子を見るのは危険です。
小さな傷だからと家で様子を見ていて、その後悪化したため受診するケースを多く診てきました。
必ず病院やクリニックを受診してください!!
特に次のような場合は、即受診が必要です:
- 傷が深い、または出血が止まらない
- 手や指を噛まれた
- 発熱や腫れが出てきた
- 糖尿病、免疫抑制治療中、高齢者など

医療機関では何をする?
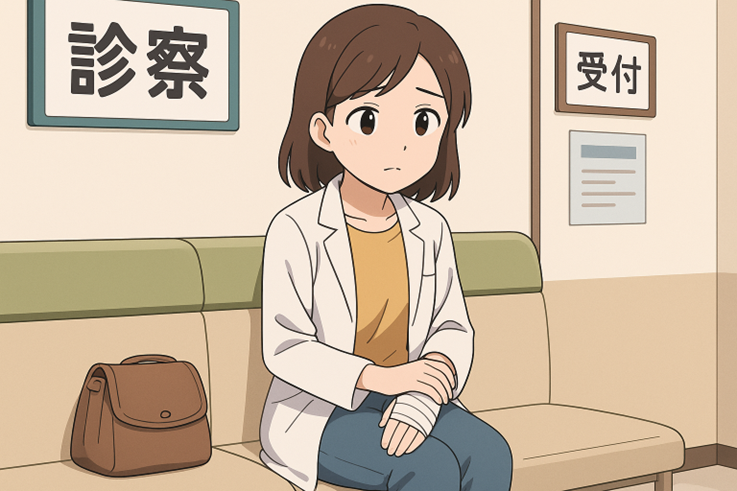
「応急処置はしたけれど、この程度で病院に行くのは大げさかな…」
そんなふうに思ってしまう方も多いですが、動物に噛まれた傷は、自己判断では見極めが難しいことがほとんどです。
医療機関では、感染のリスクを最小限に抑えるために、以下のような処置や対応が行われます。
✅ 1. 傷の確認と専門的な洗浄(デブリードマン)
まずは傷の状態を詳しく観察し、目に見えない汚れや壊死組織があれば除去します。
表面だけでなく、奥深くまで洗浄することで、感染のリスクを大幅に減らすことができます。
- 必要に応じて局所麻酔を行い、しっかりと洗浄
- 傷の場所や深さによっては、縫合せず“あえて開放”しておくこともあります(感染予防のため)
✅ 2. 抗生物質の処方
咬み傷は高確率で感染を起こすため、ほとんどの場合で抗生物質が処方されます。
- 経口抗菌薬(飲み薬)が一般的
- 猫に噛まれた傷や、手指などの深部感染リスクが高い部位では、点滴抗菌薬や入院が必要なこともあります
- アレルギー歴や基礎疾患に応じて薬を選択
✅ 3. 破傷風ワクチンの接種確認
破傷風の予防接種歴が不明な場合や、最後の接種から10年以上経っている場合には、**追加接種(トキソイド)**を行うことがあります。
- 日本では破傷風は少ないものの、死亡例もあるため重要なチェックポイントです
✅ 4. 狂犬病ワクチン(※海外での咬傷の場合)
国内で飼育されている犬・猫であれば基本的に心配はありませんが、海外での咬傷や野生動物との接触がある場合は、狂犬病ワクチンの接種が検討されます。
- 狂犬病は発症すれば致死率ほぼ100%
- 特にアジア・アフリカ・中南米などでは注意が必要
✅ 5. 経過観察と、必要に応じた外科的処置
腫れや赤み、熱感が強くなっている場合は、膿がたまっている可能性もあります。
その場合は、切開して排膿する処置が行われることも。
また、腱や神経へのダメージが疑われるときには、整形外科的な対応が必要になることもあります。
まとめ
犬や猫との暮らしの中で、ふとした拍子に噛まれてしまうことは誰にでも起こり得ます。
でも――「小さな傷だから」と甘く見てしまうのが、一番危険です。
咬み傷は見た目以上に深く、細菌が奥まで入り込んでいることも多くあります。
放置すると、腫れや感染、場合によっては手術や入院が必要になることも。
だからこそ、噛まれたら“すぐに洗う・確認する・迷わず受診する”。
この3ステップを覚えておくだけで、重症化を防ぐことができます。
心配なときには、一人で抱え込まず、遠慮なく医療機関を頼ってください。
KOY