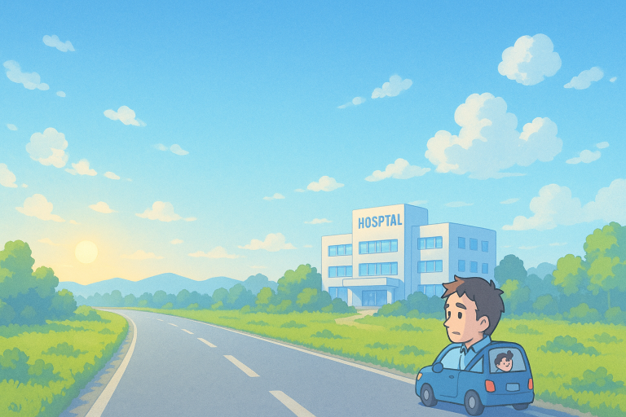
今日はいよいよ、健康診断の日——そして、人生初の「胃カメラ検査」。
「オエッてならないかな…」
「痛くないかな…」
「ちゃんとできるんだろうか…」
そんな不安な気持ち、よくわかります。
実際、胃カメラ検査を前にした患者さんからは、ほぼ毎日のようにこうした声を耳にします。
でもご安心ください。
ちょっとしたコツや準備だけで、胃カメラはグッとラクに受けられるようになります。
そして実は——
**“受ける側がラクだと、行う側(医師)にとっても、検査がとてもスムーズになる”**んです。
喉の緊張が少なければ、スコープが入りやすく、観察もしやすい。
咳き込んだり体がこわばったりしなければ、検査時間も短くなりますし、何よりお互いに安心感のある時間になります。
胃カメラが怖いのは自然なことです。
けれど「怖いけど、ちょっと頑張ってみようかな」と思ってもらえるだけで、私たち医療者は全力でサポートできます。
今回は、医師として多くの検査に立ち会ってきた経験から、
**“ラクに胃カメラを受けるための5つのコツ”**を、わかりやすくご紹介します。
これから初めて受ける方も、前回つらい思いをした方も、ぜひ読んでみてくださいね。
コツ① 鼻で深い呼吸”を意識しよう
最も多いつらさの原因は、「のどの違和感」と「吐き気をこらえる反射」です。
そして、それを強めてしまう最大の要因が“緊張”なんです。
検査が始まる直前、どうしても体がこわばってしまう気持ちはよくわかります。
でも、そんなときこそ試してほしいのが、「ゆっくりと深い呼吸」。
深く息を吸って、ゆっくり吐く。
それだけで、自然と体の力が抜け、喉や舌の筋肉も柔らかくなってきます。
特に「鼻から吸って、口からフーッと吐く」呼吸を意識すると、
のどの動きが穏やかになり、“オエッ”となる反射(咽頭反射)が出にくくなるんです。
実際、私たち医師の立場から見ても、深呼吸ができている方の検査は非常にスムーズです。
無理に力を入れるよりも、**「今は呼吸だけに集中しよう」**と気持ちを切り替えることが、何よりの近道。
本番でいきなりすると意外と難しく、逆に苦しさを感じることがあります。
前日に自宅で呼吸の練習をしましょう!
深呼吸は、道具も技術もいらない“最強の味方”です。
ぜひ検査中、ずっと続ける意識をもってみてください。

コツ②:舌と喉の力を抜いて! “のどを開く”意識を
胃カメラを入れるときに「オエッ」となってしまう原因のひとつが、舌の力みです。
特に口からの胃カメラでは、スコープが舌の根元を通るため、舌に力が入っていると、のどが狭くなり、反射が起きやすくなるんです。
つまり、「のどを開く」ためには、舌の力を抜くことがとても大切。
でも、「舌の力を抜いて」と言われても、正直よくわからないですよね。
そんなときは、次のイメージをしてみてください。
✅ あくびをしたときの“のどの奥がふわっと広がる感じ”
✅ 舌の先を軽く下の前歯の裏に触れさせて、そっと置く
✅ “飲み込まない”で、そのままゆるくしておく
この3つのポイントを意識すると、自然とのどに余計な力が入らず、通り道が広がるようになります。
力を入れてがんばるより、「だら〜んと気を抜く」くらいの方が、むしろ上手くいくんです。
そして私たち医師側も、のどがリラックスしていると、スコープを優しく、ゆっくりと通すことができ
るので、患者さんへの負担を減らせます。
「のどを開く」って、少し不思議な感覚かもしれませんが、
実はとてもシンプルで効果的なコツです。
舌や喉の力を抜くという行為は、普段するようなものではありません。
こちらも練習して検査に行くのがお勧めです!!!
ぜひ、検査中に“ふわっと広がるのど”を意識してみてくださいね。

コツ③:つばは飲まなくてOK。自然に任せよう
胃カメラを受けるとき、意外と多くの方が悩むのが
**「つばを飲んでいいのかどうか、わからない」**ということ。
喉に異物感がある状態でつばを飲もうとすると、
どうしてものどに力が入りやすく、吐き気や“オエッ”とする反射を引き起こしやすくなってしまいます。
つばが気管に入ってむせることも多々あります。
そんなときは、つばを無理に飲み込まず、自然に流れるままに任せてOKです。
むしろ、飲まないほうがラクになると感じる方が多いんです。
検査のときには、口の端からつばを出すような体勢になっていて、下に受け皿やシートを置いててくれます
「出ちゃっていいんだ」と思うだけでも、安心感がグッと増します。
私たち医療スタッフも、「つばは無理に飲まないで大丈夫ですよ」とお声かけしますので、
ぜひ「飲み込みたいけど、飲まなくていい」と、自分に言い聞かせてみてください。
つばに気を取られてしまうと、呼吸やリラックスにも集中しにくくなります。
だからこそ、“つばは自然に任せておこう”という意識が、検査全体をラクにしてくれる大切なポイントです。

コツ④:壁の一点を見る
胃カメラ中、「目のやり場に困る」「どこを見ていたらいいかわからない」という方は意外と多いです。
そんなときに有効なのが、**「壁の一点に視線を固定する」**という方法です。
たとえば、検査室の天井のシミ、照明の端、時計の枠など、
“動かないもの”の一点を見つけて、そこにじっと視線を置いてみてください。
視線を安定させることで、
無意識のうちに生まれる不安感や緊張がやわらぎ、
体全体の動きも落ち着いてくることが多いんです。
検査を行う私たち医師の立場から見ても、
視線が定まっている方は、体の動きも安定していて、非常に検査がしやすくなります。
視線がキョロキョロしていると、緊張が増して呼吸も浅くなりやすく、
結果的に検査のつらさを増幅させてしまうこともあります。
どこを見るか、なんて小さなことのように思えますが、
「ここを見る」と決めておくことが、安心感につながる大きなポイントになります。
ぜひ検査前に、“視線の着地点”をあらかじめ決めておくのがおすすめです。
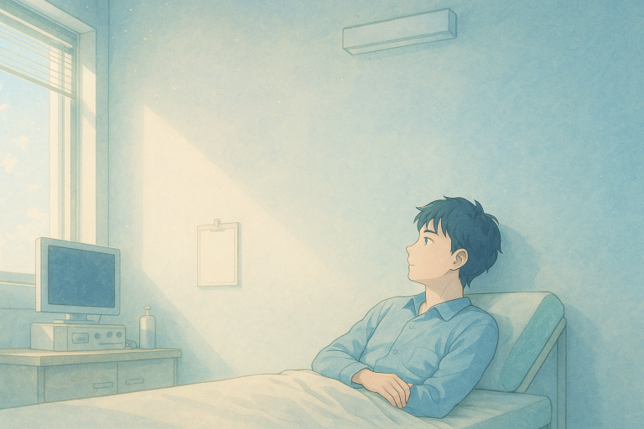
コツ⑤:事前の“喉麻酔”をしっかり受けよう
胃カメラが「つらい」と感じる一番の要因は、
スコープが通るときに起きる「咽頭反射(オエッとなる反応)」です。
この反応を軽くするためにとても大切なのが、**事前に行う“喉の麻酔”**です。
喉の麻酔は、スプレーやゼリーのような薬剤を使って、のどの粘膜を一時的にしびれさせる処置です。
これにより、スコープが喉を通るときの違和感や吐き気を大幅に和らげることができます。
ただし、麻酔が効くまでには少し時間がかかるため、
「早く検査したいから」と焦らず、きちんと麻酔の時間を取ることがとても大切です。
また、麻酔の最中には「飲み込まずに、喉の奥にためておく」というコツもあります。
これができると、麻酔の効果がしっかりと喉全体に行き渡ります。
私たち医師も、検査前に**「麻酔が十分に効いているか」を必ず確認**していますが、
ご自身でも「もう少ししっかり効かせたい」と思ったときは、遠慮せずに伝えて大丈夫です。
麻酔の効果がしっかり出ていれば、検査中の苦しさは格段に減ります。
最初のこの一歩が、胃カメラ体験を「つらい」から「思ったよりラクだった」へと変えてくれます。

まとめ・・・
胃カメラと聞くと、「つらい」「怖い」「オエッとなりそう」といったネガティブな印象が先に浮かんでしまうかもしれません。
でも、今回ご紹介したようなちょっとしたコツを知っておくだけで、そのハードルはグッと下がります。
✨おさらい:ラクに受ける5つのコツ
- リラックスがカギ!“深い呼吸”を意識しよう
- 舌の力を抜いて、“のどを開く”イメージを持とう
- つばは無理に飲まず、自然に任せよう
- 壁の一点に視線を固定して、心を落ち着かせよう
- 事前の“喉麻酔”をしっかり受けておこう
つまり、「しっかり麻酔をして、ラクにして検査をしてください」ということです。
実は私たち医療者側にとっても、患者さんがリラックスしてくださっていると、とてもスムーズに、丁寧な検査を行うことができます。
つまり、お互いにとって「ラクに受けられる準備」は大きなメリットになります。
不安を完全になくすのは難しいかもしれません。
でも「ちょっとだけ意識してみよう」「少し気が楽になった」と思っていただけたら、それだけで十分です。
このブログが、あなたの検査の不安を少しでも和らげる助けになれば、医師としてこれ以上嬉しいことはありません。
他にも、声をかけてもらうことで安心感が得られたり、つらい時に背中をさすってもらすと軽減するなどもあります。
また、施設によっても細かいところで対応方法はかわってきます。その施設での対応に従って頑張ってください!
どうか安心して、検査に臨んでください!
KOY
参照サイト:住吉内科消化器内科クリニック、看護師ブログ