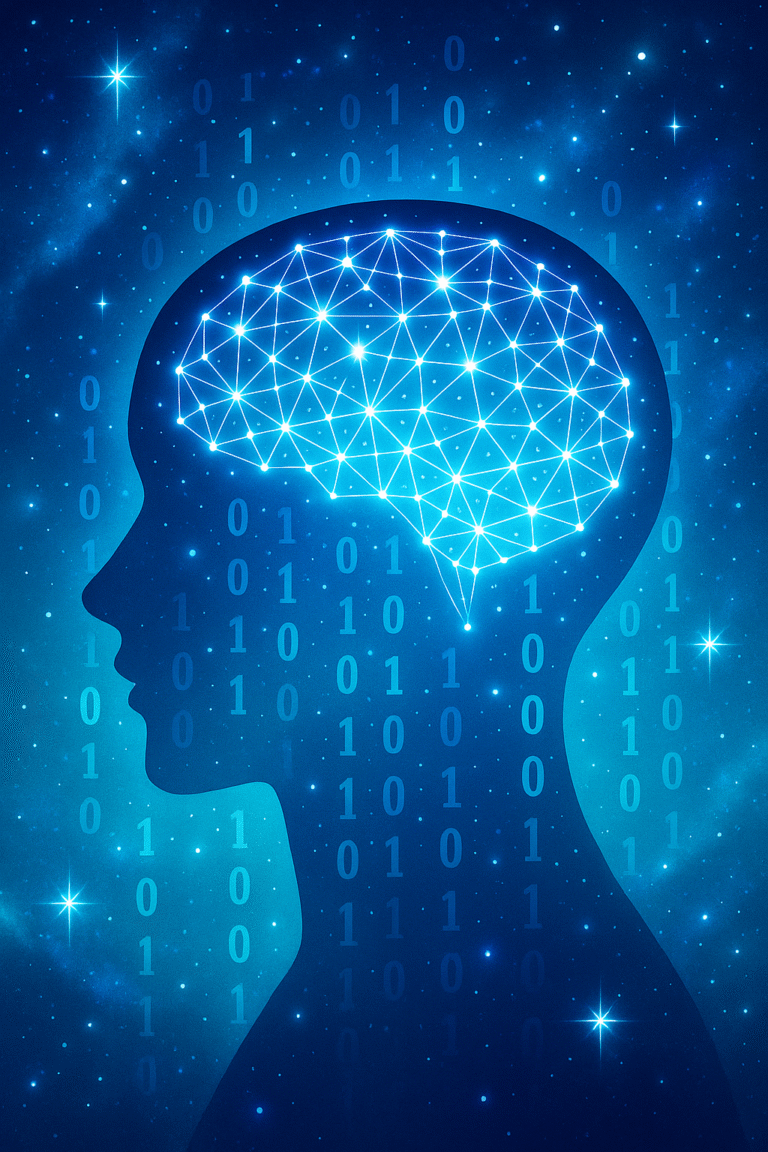最近、身近な人が同じ話を繰り返すようになったり、今が何月か分からなくなったりしていませんか?
あるいは、自分自身の物忘れに「これって大丈夫かな…」と不安を感じたことはありませんか?
認知症は、年を重ねれば誰にでも起こりうる、身近な病気です。
でも、「年のせい」と見過ごしてしまうと、大切なサインを見逃してしまうことも。
この記事では、認知症の特徴や物忘れとの違い、原因、予防のヒントまで、
専門的なことも分かりやすくやさしく、2回に分けて解説します。
第1章:認知症とは
~「物忘れ」との違い、知っていますか?~
「認知症」という言葉、ニュースや身近な会話でもよく耳にするようになりました。
でも、実際にどんな病気なのか、詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか?
認知症とは、脳の細胞がさまざまな原因で壊れてしまい、記憶や判断力、理解力などが少しずつ低下していく病気です。
その結果、日常生活に支障が出るようになります。
たとえば、こんなことが起こるようになります:
- 今日の予定を忘れてしまう
- 財布やカギの置き場所が分からなくなる
- 時間や場所の感覚があいまいになる
- 知っている人の名前がすぐに出てこない
ここでよくあるのが、「年のせいの物忘れ」との混同です。
実は、物忘れと認知症は、似ているようで大きく違うんです。
| 年相応の物忘れ | 認知症 | |
|---|---|---|
| 忘れる内容 | 一部を忘れる(例:話の細かい内容) | 体験そのものを忘れる(例:話したこと自体) |
| 気づき方 | 自分で「あれ?」と気づく | 本人は気づかず、周囲が気づくことが多い |
| 日常生活への影響 | ほとんどない | 支障が出ることが多い |
つまり、「ちょっとした物忘れ」=すぐに認知症、ではありません。
でも、「最近なんだか様子が変だな」と感じることが重なってきたら、
それは認知症の始まりのサインかもしれません。
大切なのは、早めに気づいて、できる対策を知ること。
第2章:どんな症状が出るの?
~「ちょっとおかしいな」と思ったときがサイン~
認知症の症状は、人によって現れ方がさまざまですが、大きく分けて2つのタイプに分けられます。
🧠① 中核症状:脳の働きが落ちることで起こる基本的な変化
これはすべての認知症の方に共通して見られる症状です。以下のような特徴があります。
✔ 記憶障害(もの忘れ)
- 同じ話を何度も繰り返す
- さっき食べたご飯のことをすっかり忘れて「まだ食べてない」と言う
- 大切な予定(病院や友人との約束)を忘れてしまう
✔ 見当識障害(時間や場所の感覚のズレ)
- 「今日は何日?」と何度も聞く
- 昼なのに「そろそろ夕飯の時間でしょ?」と言う
- 自宅なのに「ここはどこ?帰らなきゃ」と言い出す
✔ 判断力・理解力の低下
- お釣りの計算ができなくなる
- 電話や電化製品の操作が難しくなる
- 料理の手順がわからなくなり、火をつけっぱなしにしてしまう
🌀② 行動・心理症状(BPSD):本人の不安や混乱から起こる反応
これは中核症状が進行した結果、周囲との関係や環境から影響を受けて現れる症状です。人によって強く出る場合と、ほとんど出ない場合があります。
✔ 妄想や被害的な言動
- 「お金を盗られた!」と家族を疑う
- 「あの人は私をいじめている」と言い出す
✔ 感情の起伏が激しくなる
- 急に怒り出す、逆に笑いが止まらなくなる
- 小さなことで泣いてしまう
✔ 徘徊
- 家を出て、目的もなく歩き回ってしまう
- 「家に帰る」と言って、今いる家から出て行こうとする
✔ 睡眠障害
- 夜中に何度も起きる、昼夜逆転する
- 早朝に目覚めて家の中を歩き回る
🌱家族が気づくことが多い
認知症の初期では、本人は「自分が変わった」ことに気づかないことが多いため、最初に違和感を抱くのは家族や周囲の人です。
「最近、少し様子が変わったな」
「前はできていたことが、うまくいかなくなってるかも」
そんな気づきが、認知症の早期発見につながります。
📌大事なのは「責めない・焦らない・寄り添う」
これらの症状は、本人の“性格の問題”ではなく、病気によるものです。
大切なのは、本人を責めず、ゆっくりと関わっていくこと。
「何度も同じこと言ってるでしょ!」ではなく、
「そうだったね、ありがとう」とやさしく受け止めることで、
不安や混乱を和らげることができます。
第3章:認知症の種類と原因
~すべての認知症が「同じ」ではありません~
「認知症」と聞くと、ひとつの病気のように思われがちですが、実はいくつかの“タイプ”があります。
それぞれ原因や特徴が異なり、症状の出方や進行の仕方も違います。
ここでは、代表的な4つの認知症をご紹介します。
🧩① アルツハイマー型認知症
最も多いタイプで、**全体の約60〜70%**を占めます。
✅特徴:
- ゆっくりと進行する
- 最初に「記憶力の低下」が目立つ(特に新しいことを覚えられない)
- 脳の中に「アミロイドβ」などの異常なたんぱく質がたまり、神経細胞が壊れていく
📝こんな様子が見られます:
「何度も同じことを聞く」
「財布やカギの置き場所を忘れる」
「食べたこと自体を忘れてしまう」
🧠② 脳血管性認知症
脳梗塞や脳出血など、脳の血管に障害が起きたあとに発症するタイプです。
✅特徴:
- 症状に“ムラ”がある(良い日と悪い日がはっきり)
- 感情のコントロールが難しくなることも
- 手足の麻痺や言葉のもつれを伴うことが多い
📝こんな様子が見られます:
「急にできないことが増えた」
「怒りっぽくなった」「涙もろくなった」
「歩き方がふらつく」
👁③ レビー小体型認知症
**幻視(見えないものが見える)**が特徴的なタイプです。
「レビー小体」という異常なたんぱく質が脳にたまることで発症します。
✅特徴:
- 幻視(虫や人が見えるなど)が比較的早くから現れる
- 体がこわばる(パーキンソン症状)
- 日によって頭のはっきり具合に波がある
📝こんな様子が見られます:
「部屋に知らない人がいる」と言う
「床に虫がいる」と言って掃除を始める
「今日は普通に話せるけど、昨日は全然会話にならなかった」
🗣④ 前頭側頭型認知症(ピック病など)
比較的若い年代(50〜60代)に発症することもあるタイプです。
✅特徴:
- 感情のコントロールが難しくなる
- 社会的なルールを守れなくなる
- 言葉が出てこなくなる(失語)
📝こんな様子が見られます:
「突然怒鳴ったり、人に暴言を吐くようになった」
「同じ物ばかり食べたがる」「お金を無駄遣いする」
「会話の中で言葉が極端に少なくなった」
🔍原因はさまざま。でも「早期発見」が共通のカギ。
認知症の原因には、
- 加齢による脳の変化
- 生活習慣病(高血圧・糖尿病など)
- 脳血管の障害
- たんぱく質の異常蓄積 などがあります。
しかし、どのタイプの認知症でも早めに気づいてサポートを始めることが、
その後の生活の質を守る大きなカギになります。
まとめ・・・
症状についてなんとなくイメージがつきましたでしょうか?
私たちが日常で「最近物忘れが多くて・・・、認知症かも~」
と話すことがあると思いますが、それとは全然違うと感じましたでしょうか。
2回に分けてお送りさせて頂いております。 次の記事では診断や治療、予防について説明していきます!
KOY