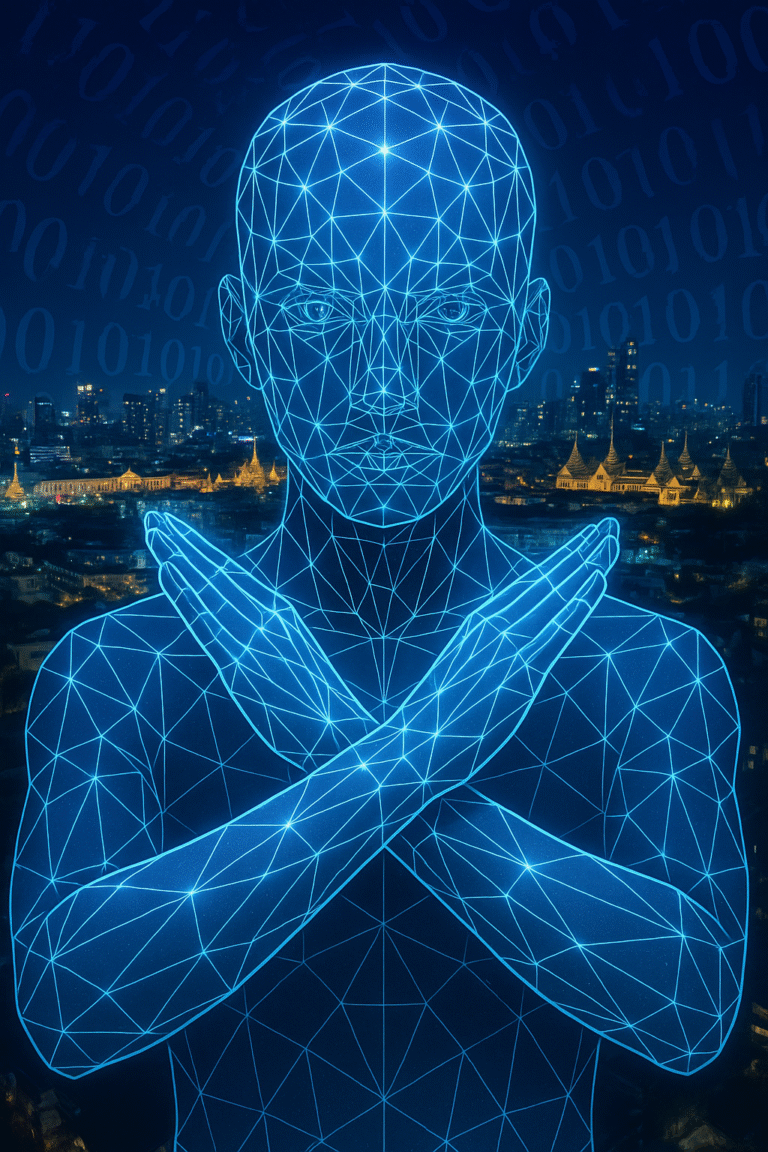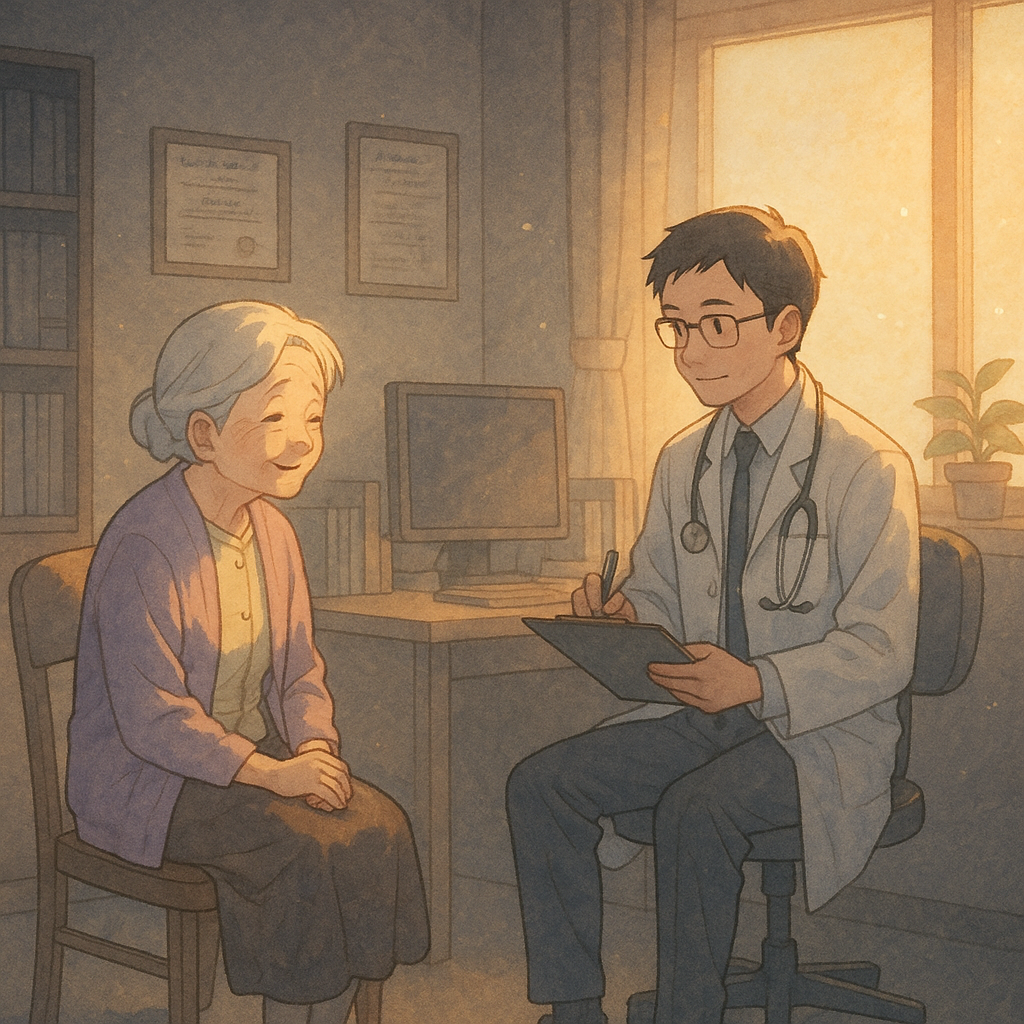
前回の認知症についての続きです。
今回は診断や治療、予防について説明していきます。
前回の記事の症状に家族の方が思い当たるものがあれば、認知症外来を受診することをお勧めします。
前回ブログ記事:認知症ってなに? 違いについて説明できますか? 〜物忘れとはちょっと違う~②
他サイト:認知症ネット
第4章:どうやって診断するの?
~「年のせいかな」と思ったら、一度相談してみて~
認知症は、早めに気づいて対応することで、進行をゆるやかにしたり、本人や家族の負担を軽くできる病気です。
でも、「病院に行くのはちょっと抵抗がある…」「まだ様子を見たい…」と迷う方も多いのではないでしょうか?
ここでは、実際にどんな方法で認知症の診断が行われるのかを、やさしく説明します。
📝1. 問診(お話を聞くこと)
まず大切なのは、ご本人やご家族から話を聞くことです。
- いつ頃から、どんな変化があったか
- 普段の生活で困っていること
- これまでの病気やお薬の内容
- 家族の様子や支援の状況 など
医師は、この情報をもとに「その人らしさ」を理解しながら、症状の背景を考えていきます。
ご家族が一緒に受診されると、より正確な診断に役立ちます。
🧠2. 認知機能のテスト
「物忘れがある」と言っても、どのくらいの程度なのかは人によって違います。
そのため、いくつかのテストを使って記憶力や判断力を確認します。
代表的な検査:
🟡 長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)
- 名前・年齢・日付などを答える
- 簡単な計算や、言葉の復唱をする
→ 日本で広く使われている検査です
🔵 MMSE(Mini Mental State Examination)
- 世界中で使われている、国際的な認知機能テスト
- 記憶、注意力、言語理解など、幅広い項目をチェック
💡どちらも10〜15分ほどで終わる簡単なテストで、苦痛を伴うものではありません。
🖥3. 画像検査(脳の状態をみる)
脳の構造に異常がないか、また認知症のタイプを見分けるために、脳の画像を撮る検査が行われます。
- MRI:脳の萎縮(小さくなる)や血流の低下を詳しく見る
- CT:脳出血や脳梗塞などの有無をチェックする
- SPECT(スペクト):脳の血流を調べる(必要に応じて)
これらの検査で、アルツハイマー型や脳血管性など、認知症のタイプを推測することができます。
💉4. 血液検査や身体のチェックも大切
認知症と似たような症状を起こす病気(※「認知症もどき」と呼ばれることも)を見つけるために、血液検査や身体のチェックも行われます。
例えば:
- 甲状腺ホルモンの異常
- ビタミン不足(特にB12)
- 薬の副作用
- うつ病 など
これらは治療で改善する可能性があるため、「本当に認知症かどうか」を見極めるうえでとても重要です。
🌈診断は“ラベルを貼る”ことではありません
「認知症と診断されたら終わり…」と思っていませんか?
それは誤解です。診断は、その人の状態を正しく知り、これからどうサポートしていくかを考えるためのスタート地点。
決して“人生の終わり”ではなく、“安心の第一歩”です。
🧩受診のタイミングはいつ?
こんなことが増えてきたら、一度ご相談をおすすめします。
- 同じ話を何度も繰り返すようになった
- 物の置き場所を頻繁に忘れる
- 予定をよく間違えるようになった
- 時間や場所の感覚があいまいになってきた
- 料理や買い物などがうまくできなくなった
第5章:治療や対応は?
~診断はゴールではなく、“これから”のためのスタート~
「認知症です」と診断されたとき、多くの方が「これからどうすればいいの?」と不安になります。
でも、認知症と診断されたからといって、すぐに何もできなくなるわけではありません。
ここでは、治療や生活での対応、家族の関わり方について、わかりやすくお伝えします。
💊1. 認知症の進行をゆるやかにする薬
現在の医学では、認知症を「完全に治す薬」はまだありませんが、
症状の進行をゆっくりにしたり、不安や混乱をやわらげる薬がいくつかあります。
主な薬の種類:
- コリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジルなど)
→ 記憶力や集中力の改善に使われることが多い - NMDA受容体拮抗薬(メマンチン)
→ 興奮や混乱、攻撃的な症状をやわらげることがある
症状のタイプや進行度に応じて、医師が慎重に選びます。
副作用にも注意しながら、**“薬はあくまで一つの手段”**として使っていくのがポイントです。
🏠2. 日常生活での工夫と支援
認知症のある方が、少しでも自立して生活できるように支える工夫が大切です。
✅ 家の中の工夫
- よく使う物の場所を決めて、ラベルを貼る
- ストーブやガスは自動停止機能付きに
- 日めくりカレンダーやホワイトボードで予定を見える化する
✅ 外出や運動のすすめ
- 散歩や体操など、無理のない運動を習慣に
- 地域のサロンや集まりに参加することで、刺激や安心感が生まれます
💡**「できないこと」に注目するのではなく、「まだできること」を一緒に見つける**ことが、本人の自信と笑顔につながります。
👪3. 家族の関わり方~イライラしないために~
認知症のケアで一番大切なのは、家族の関わり方です。
でも、実際には「何度も同じことを言われてつらい…」「どう接していいかわからない」という声も多いのが現実。
✔ 家族が気をつけたいポイント
- 否定しない:「そんなこと言ってないでしょ!」ではなく「そうだったんだね」と共感
- 怒らない:イライラは相手にも伝わって、症状が悪化することも
- 思い出そうとさせない:「昨日なに食べた?」ではなく「昨日はカレーだったね、美味しかったね」と一緒に振り返る
💡家族ががんばりすぎると、共倒れになってしまうこともあります。
「無理をしない」「誰かに頼る」ことも、大切なケアの一つです。
🧩4. 地域や制度のサポートも活用しよう
認知症のケアは、家庭だけで抱え込まないことが大切です。
日本では、以下のような制度やサービスが整備されています。
🟡 地域包括支援センター
→ 高齢者の総合相談窓口。介護保険の申請や、どんな支援が受けられるか教えてくれます。
🟡 ケアマネージャー
→ 介護保険サービスの手配・調整をしてくれる専門職。心強い味方になります。
🟡 認知症カフェ・家族会
→ 同じ悩みを持つ人たちと交流したり、専門家のアドバイスが受けられる場です。
🌈認知症と「共に暮らす」ために
認知症と診断されても、
本人が自分らしく生きること、
家族が笑顔で寄り添うこと、
その両方は**「知ること」「話し合うこと」**で実現できます。
困ったときは一人で抱えず、周囲に頼ってください。
「病気だからこそ、つながりが必要」――その意識が、本人にも家族にも優しい未来をつくります。
第6章:認知症は予防できるの?
~毎日の小さな習慣が、未来の自分を守ります~
「認知症って、年をとったら仕方がないものじゃないの?」
そう思われがちですが、実は最近の研究では、生活習慣の改善や社会とのつながりを保つことで、認知症のリスクを減らせる可能性があることがわかってきました。
認知症を“完全に防ぐ”ことは難しくても、「なりにくくする」「進行をゆるやかにする」ことは、今からでもできるんです。
🧠1. 頭を使うことを習慣にしよう
脳も筋肉と同じで、使わないと衰えてしまうものです。
💡おすすめの“脳トレ”習慣
- 日記やメモを書く
- 新聞を音読する
- パズルやクロスワード、将棋などに挑戦
- 新しい趣味や勉強(料理・楽器・語学など)
💬 ポイントは、「ちょっと難しい」と思うくらいのことに楽しくチャレンジすること。脳がぐんと刺激されます。
🚶♀️2. 体を動かして、脳も元気に
運動は脳への血流を増やし、神経細胞の働きを保つ効果があることがわかっています。
✅こんな運動がおすすめ!
- 毎日のウォーキング(1日20〜30分を目安に)
- ラジオ体操やストレッチ
- ダンスやヨガなど、リズムに合わせた運動
💡できれば「人と一緒に楽しむ」ことがさらに効果的!笑顔で体を動かせると、気分も上がります。
🍚3. 食事は“バランス”と“彩り”を意識して
脳の健康は、毎日の食事からつくられます。
🥦脳にやさしい食材
- 魚(特に青魚に含まれるDHA・EPA)
- 野菜・果物(抗酸化作用のあるビタミンが豊富)
- ナッツ類(良質な脂質とミネラル)
- 大豆・納豆など(たんぱく質源としても◎)
📝 塩分・糖分・脂肪の摂りすぎには要注意!
“地中海食”のような野菜と魚中心の食事は、認知症予防に効果があるとされています。
🧑🤝🧑4. 人とのつながりが、脳を守る
社会的な孤立は、認知症のリスクを高める大きな要因の一つ。
人と関わることは、記憶・感情・判断など、脳のあらゆる部分を刺激する最高の脳トレなんです。
☕こんな習慣を意識してみましょう
- 家族や友人とのおしゃべりを大切にする
- 地域の集まりやサークルに参加する
- ボランティアや習い事を始めてみる
💡「話す」「笑う」「一緒に過ごす」――それだけで、心も脳も元気になります!
🛌5. 睡眠・ストレスにも気をつけて
睡眠中、脳は老廃物(アミロイドβなど)を“お掃除”する時間でもあります。
睡眠不足が続くと、脳の負担がたまりやすくなります。
- 規則正しい睡眠リズムを
- 寝る前はスマホを控えて、リラックスできる環境を
- 昼寝は短め(20分以内)に
また、ストレスも脳の働きに影響します。
自分なりのリフレッシュ方法を見つけて、気持ちの切り替えも大切にしましょう。
まとめ・・・
長い記事を最後まで読んで頂いてありがとうございました。
勉強になったでしょうか
少しでも認知症について理解していただき、早めの対応、予防などに取り組んでいただけると嬉しいです!
また、家族に認知症の方がいる家庭でも記事を参考にしてもらえると幸いです。
今後、認知症の方が少しでも減ること、そして理解ある世の中になることを願っています。
KOY