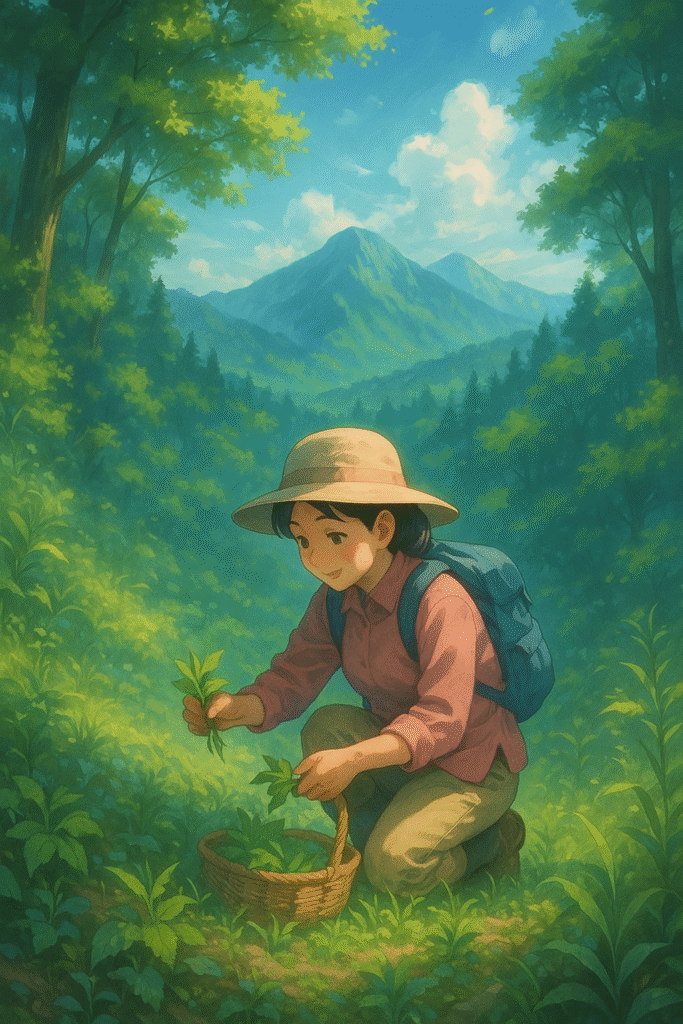
2025年7月、神奈川県でマダニが媒介する感染症「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」の感染が確認されました。
関東地方での感染報告はこれが初めてで、県内で感染したとみられています。
これを受けて、県は注意喚起を行っています。
当ブログでは、マダニ感染状況についてこれまでも紹介してきました。他の記事も参考にしてください。
※ニュースの概要:マダニが媒介の感染症SFTS 神奈川の女性感染 関東では初
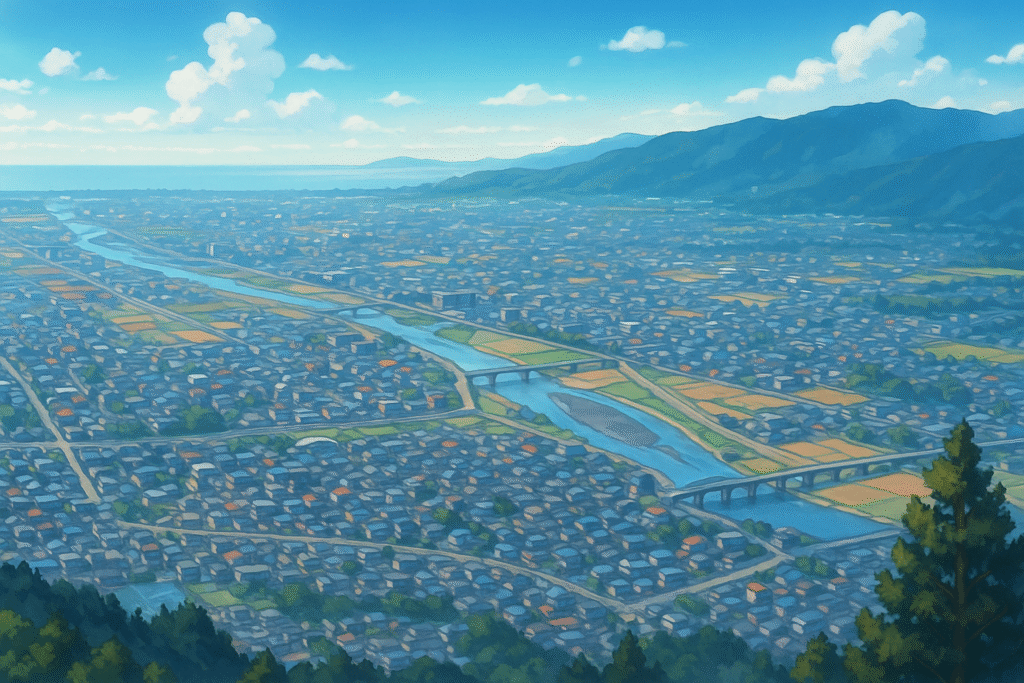
2025年7月2日、神奈川県松田町に住む60代の女性が発熱などの症状を訴えて医療機関を受診し、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」と診断されました。
SFTSはマダニを介して感染するウイルス性の感染症で、発熱や消化器症状を伴い、重症化すると意識障害や死亡に至ることもあります。
神奈川県が行った調査によると、この女性には県外への外出歴や他の感染者との接触歴がなく、県内で感染したとみられることが分かりました。
県内感染と判断されたのはこれが初めてで、関東地方におけるSFTSの感染確認は今回が初めてです。
なお、今年は全国的に感染者数が増加傾向にあり、6月29日までの半年間で報告されたSFTS患者数は全国で91人に上っており、これは過去最多となっています。
この事態を受けて神奈川県は、野外で活動する際には長袖・長ズボンを着用して肌の露出を避け、虫よけスプレーを使用するなどの対策を講じるよう県民に呼びかけています。
STFSとは?
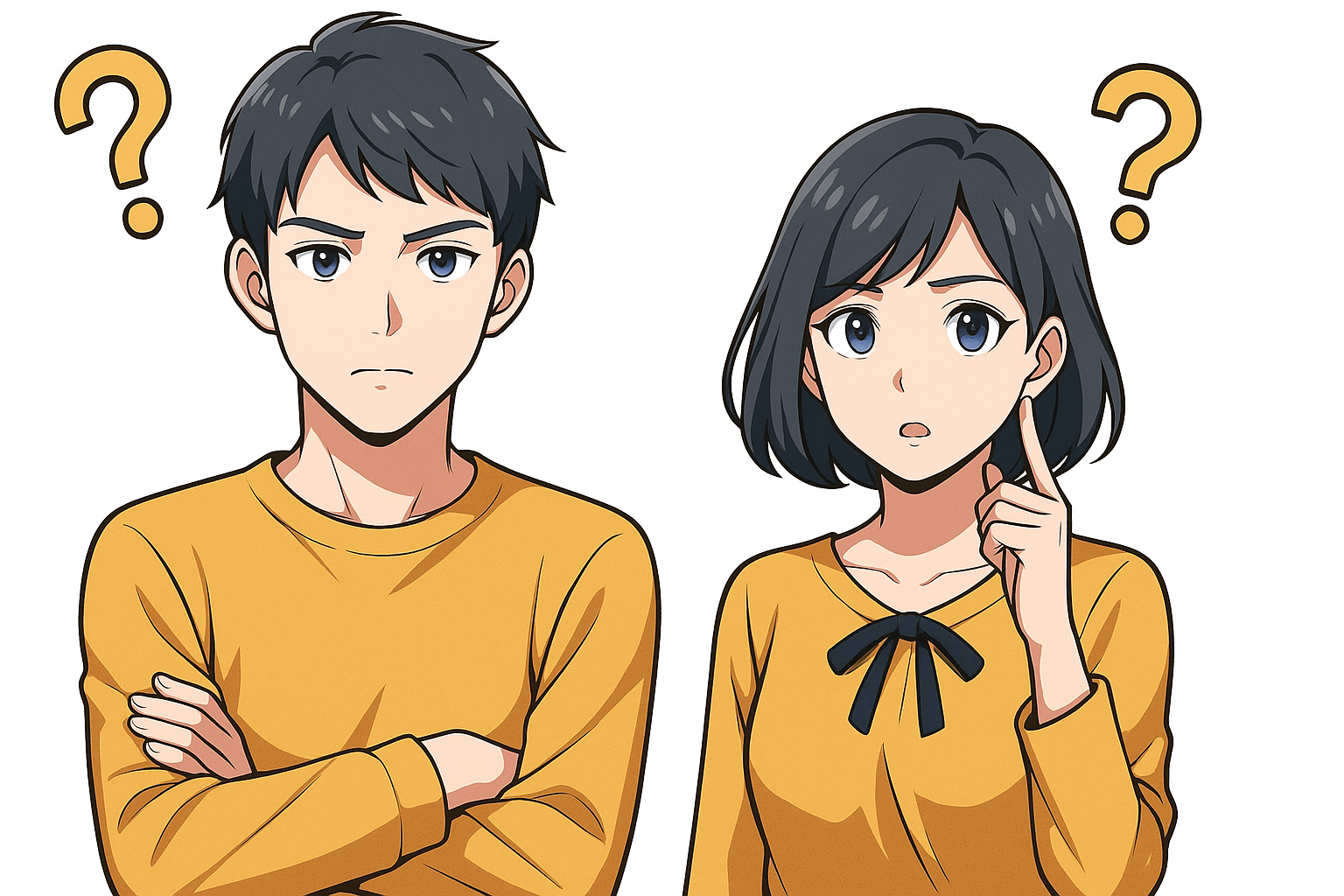
SFTS(重症熱性血小板減少症候群:Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)は、主にマダニを介して人に感染するウイルス性の感染症です。2011年に中国で初めて報告され、日本でも2013年以降、西日本を中心に患者の報告が続いています。
このウイルスは「SFTSウイルス(SFTSV)」と呼ばれるブニヤウイルス科の一種で、ヒトからヒトへの感染は稀ですが、血液や体液を介した感染が報告された例もあります。
主な症状
感染後の潜伏期間はおよそ6〜14日間とされ、その後以下のような症状が現れます:
- 発熱(38度以上)
- 倦怠感(だるさ)
- 食欲不振
- 吐き気・嘔吐・下痢などの消化器症状
- 血小板や白血球の減少
- 重症例では意識障害やけいれん、多臓器不全に進行することもあります。
致死率とリスク
SFTSの致死率は10〜30%程度と高く、特に高齢者や基礎疾患を持つ人では重症化しやすい傾向があります。
また、早期に診断し、支持療法(対症療法)を行うことが重要ですが、現時点で特効薬やワクチンは存在しません。
感染経路と季節性
- 主な感染経路は、マダニに咬まれることによるウイルス感染です。
- 感染リスクが高まるのは、マダニの活動が活発になる春から秋(4月〜10月)。
この病気は、どこか遠くのものではなく、私たちの身近な自然の中に潜むリスクです。
今回のように神奈川県内での感染が報告されたことで、今後は関東地方においてもより一層の注意が必要になってきます。
マダニってどんな虫?

「マダニ」と聞くと、小さな虫であまり気にとめない人もいるかもしれません。
しかし、実はマダニはさまざまな感染症を媒介する、非常に注意すべき吸血性の節足動物です。
■ 見た目と特徴
- 体長は成虫で3〜4mm程度ですが、吸血すると10mm以上に膨れ上がります。
- クモの仲間で、足は8本あります。
- 色は赤褐色〜黒っぽい色をしており、草むらや落ち葉の中に潜んでいます。
■ 生息場所と活動時期
- 主に山林、草地、畑の周辺、あぜ道、河原、公園の茂みなどに生息しています。
- 野生動物(イノシシ、シカ、野ウサギなど)に寄生して広がっており、
人が野外に入ることで接触するリスクが高まります。 - 活動が活発になるのは**春から秋(4月〜10月)**です。
■ 吸血の方法
- マダニは、草や葉の先端でじっと待ち伏せし、通りかかった動物や人にしがみつきます。
- 皮膚にしっかりと口器を突き刺し、数日間にわたって吸血します。
- 咬まれても痛みがほとんどないため、気づかないうちに吸血されていることが多いのも厄介な点です。
■ 媒介する感染症
マダニは今回のSFTSだけでなく、以下のような感染症も媒介します:
- 日本紅斑熱
- ライム病
- Q熱
- ダニ媒介脳炎(海外) など
いずれも重症化する可能性があり、特にSFTSは人命に関わる感染症として注目されています。
感染予防は何すすればよい?
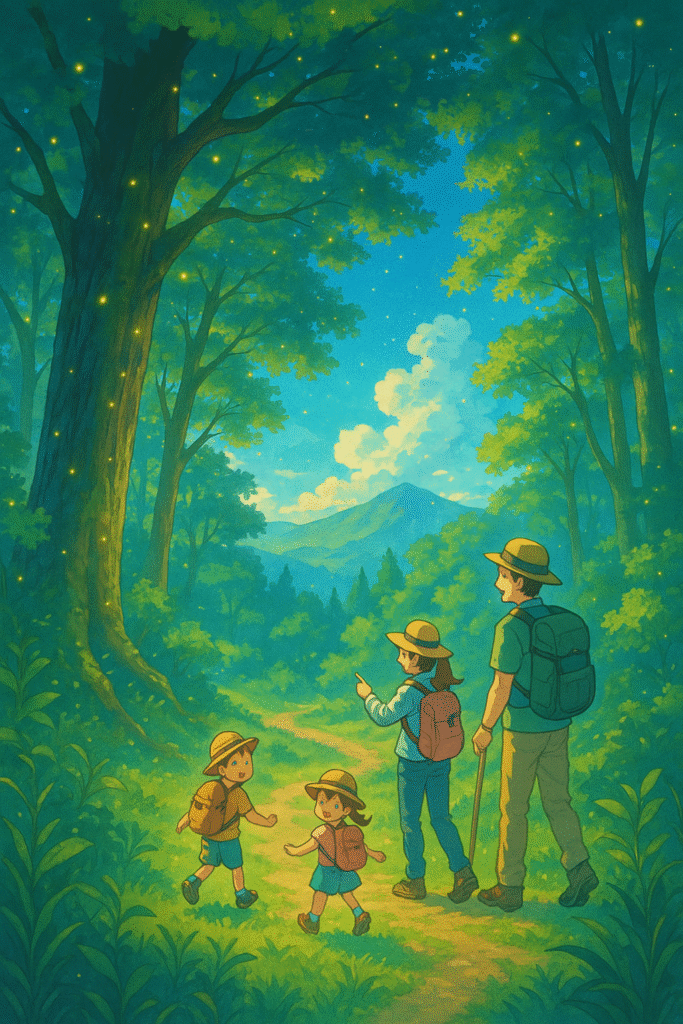
SFTSなどのマダニ媒介感染症は、“咬まれないこと”が最大の予防策です。
山や草むらに入るときには、ちょっとした注意と対策で感染のリスクを大きく減らすことができます。
■ 1. 服装を工夫する
マダニは肌の露出した部分に付着しやすいため、以下のような服装を心がけましょう。
- 長袖・長ズボンを着用する
- ズボンの裾は靴下やブーツの中に入れる
- 帽子や手袋も有効
- 服の色は明るい色(マダニを見つけやすくする)
■ 2. 虫よけスプレーを使う
ディートやイカリジンを含むマダニ対応の虫よけスプレーを、
- 肌の露出部
- 衣服の上
にしっかり吹きつけましょう。
効果は時間とともに薄れるため、こまめな再塗布が大切です。
■ 3. 外出後はマダニチェックを!
野外活動後には、以下を忘れずに確認しましょう:
- **身体(特に耳の後ろ、脇、足の付け根など)**にマダニがついていないか
- 衣服や持ち物、ペットの体にマダニがついていないか
- シャワーを浴びる際に皮膚を丁寧に確認することも有効です
■ 4. マダニを見つけたら?
もしも皮膚にマダニがくっついていた場合、無理に引き抜かないでください!
口器が皮膚内に残ると感染リスクが高まるため、
→ すぐに医療機関で適切な処置を受けましょう。
■ 5. ペットにも注意を
犬や猫が野外に出ると、マダニを連れて帰ってくることがあります。
- 散歩後はペットの体をチェック
最後に・・・
記事を読んでいただいてありがとうございました。
当ブログではマダニのニュースを何回か取り上げてきましたが、
それはマダニ感染者が多くなっていて、ニュースになることが多くなっている証拠だと思います。
夏は暑いですが、アウトドアの季節でもあります。
少しでも気を付けるべき知識をつけて、楽しい夏を思いっきり過ごせるように今年も楽しんでください!
KOY
